暗殺者
フェリックス・ユスポフ王子は殺人者としては考えにくい人物だった。世界一の財産を持つという噂の唯一の相続人であるユスポフは、色白で女装癖があり、スキャンダラスな浮気をするような、変わった男であった。彼が冷徹で計算高い暗殺者であったとは想像しがたい。ラスプーチンを殺した理由は謎に包まれているが、1919年にロシアから逃亡した後、その犯罪に関する詳細な記録をいくつか発表している。それでも、最近になって、この殺人事件における彼の役割が疑問視されている。ユスポフは自分の行動に対して開き直った態度を変え、ロシアを革命から救うことだけが自分の望みであると主張した。1916年12月の事件後、王子は自分の悪名と、彼を取り巻く謎めいた空気を楽しんでいた。
ユスポフは1887年、首都モイカ運河沿いの巨大な邸宅で誕生した。新古典派様式の広大な宮殿は、エカチェリーナ大帝から一族に贈られたもので、舞踏室、サロン、アートギャラリー、プライベートシアターなどを備えていた。ユスポフ家はタタール人の出である。先祖のイスラム教徒が政治的な理由で正教会に改宗して以来、一族はロシア宮廷の常連となった。ユスポフ一族は大富豪となり、一族が所有する邸宅はあまりにも広く多数あり、一族で数カ所しか訪問したことがないほどだった。
ユスポフの母ジナイダは美しく、芸術的で、社交的であり、フェリックスを溺愛した。一方、父親は不愛想で距離を置いていた。 父のフェリックス・スマロコフ=エルストン伯爵は、若い頃、無一文の衛兵将校だった。ジナイダと結婚したとき、彼はアレクサンドル3世の許可を得て、ユスポフ・スマロコフ=エルストンを名乗り、自分の死後も家名を存続させることにした。
幼いフェリックスは、両親の相反する影響力を、操り、避け、交渉することを学んだ。フェリックスは、母親がどうしても女の子を欲しがっていたため、もう一人の息子が生まれ、がっかりしていたことに気づき始めた。ジナイダは息子が5歳になるまでドレスを着せていたが、実はこれは当時のヨーロッパの貴族の間ではかなり一般的な習慣だった。父親はフェリックスを弱く、女々しく、変わり者とみなしていた。甘やかされ、わがままなフェリックスの要求に「ノー!」と答えることはほとんどなかった。彼は驚くほど美しい青年に成長し、12歳で母親のガウンを着るようになった。兄のニコライは、彼をおしゃれなレストランやカフェに連れて行き、そこでフェリックスは男たちの興奮を浴びることを覚えた。父親はこのような冒険を恐れていたが、フェリックスはそれを諦めなかった。サンクトペテルブルクの上流社会の人々のように、彼はすぐに神秘主義、アヘン、そして禁断の快楽をささやくあらゆるものに手を出した。
フェリックスは陰謀を好み、知らず知らずのうちに兄の死に重要な役割を果たすことになる。兄ニコライが既婚の貴族と交際するのを勧め、密会を取り持ち、激怒した夫が決闘で愛人を殺すまで交際を続けた。フェリックスは罪悪感に苦しみ、皇后の妹で同情的な大公妃エリザヴェータ・フョードロヴナ(エラ)を頼った。彼女は夫を革命派に殺された後、修道女となりシスターの修道会を率いていた。エラは、若い王子に同性愛を恥じることはない、と言い聞かせた。1909年、フェリックス・ユスポフはオックスフォード大学に入学した。しかし、彼はパーティーで過ごすことが多く、できる限りのぜいたくな生活を送っていた。
フェリックスは1913年にはロシアに戻り、皇帝の妹クセニアとその夫アレクサンドル・ミハイロヴィチの娘イリーナとの結婚を求めた。ユスポフの派手な過去にもかかわらず、二人は1914年2月に結婚した。ロシアの皇帝一族と最も裕福な一族が結ばれるという、この時期の社会的なイベントであった。花嫁はマリー・アントワネットが持っていたレースのベールをつけて、金ピカの馬車で到着し、アレクサンドラからは素晴らしいダイヤモンドのコレクションが贈られた。結婚生活はそれなりに幸せなものだった。1915年には娘(イリーナ)が生まれたが、フェリックスは若い美しい男性を追い求めることをやめなかった。
ユスポフとラスプーチンは1909年に初めて会った。グレゴリーはこのハンサムな若い王子をとても気に入り、マレンカヤ(小さい人)という愛称までつけた。一方、ユスポフはグレゴリーを本能的に嫌っていた。しかし、1913年にジナイダがラスプーチンの宮廷での影響力を批判し始めるまで、彼のことをほとんど気にも留めていなかった。ジナイダは自分の意見を皇后に伝えるという致命的なミスを犯し、不名誉なことに宮殿から追い出されてしまった。1915年、ユスポフの父は、5月にモスクワを襲った反ドイツ暴動を制止できなかったため、モスクワ総督を解任された。ユスポフ夫妻は、年老いた王子の限界と失敗を認識することができず、これらの不幸はなぜかラスプーチンのせいであると確信していた。実際、若いフェリックスは、不安定な皇后と、その弱い夫のおかげで、ラスプーチンがロシアを破壊していると考えるようになった。そして、ラスプーチンを憎み、ロシアを脅かすこの男を滅ぼすことが自分の使命であるとユスポフは考えるようになる。
ユスポフは、前線での重要なイベントは、アレクサンドラとラスプーチンの事前会議なしで決定されたことはない、という思いにとらわれた。彼は、ラスプーチンはドイツのスパイであるか、少なくともロシアの敵との個別和平を求める人々と協調して行動していると確信していた。彼の推薦で大臣が出入りし、彼のお気に入りは正教会を破壊していた。ニコライ2世はそれを止めることができないし、止めようともしないので、誰かがロシアを救わなければならない。そして、その誰かとは、ユスポフの妄想の中では、自分自身であった。
少なくとも、これがユスポフが歴史に示した理想主義的な顔である。しかし、中には懐疑的な見方もある。一部の人たちは、ユスポフが「注目の的」になることに貪欲で、栄光の夢を見るような男であると指摘した。ラスプーチンを殺せば、彼は「ロシアの救世主」になれる。
ユスポフの性格は、冷徹で計算高い殺人者というプロファイルとは相容れないものであり、計画の発端は別のところにあるとする説もある。アレクサンダー・ボカーノフ氏は、高名な弁護士で下院議員のワシリー・マクラコフ氏がその役割を果たしたと主張したが、マクラコフ氏が暗殺者の顧問以外の役割を果たしたという証拠はない。最近の学説では、英国秘密情報部に責任があるとされている。第22章で見るように、ユスポフはおそらくイギリスの諜報員と計画について話し合ったのだろう。しかし、ラスプーチンの死が英国防諜の「汚い策略」であったという証拠はあまりない。
ラスプーチンの死は、皇帝の従兄弟であるニコライ・ミハイロヴィチ(一族の間では「ビンボー」と呼ばれていた)が仕組んだとする説もある。大公は著名な歴史家であり、ニコライ2世の無能さを非難する文人であり、またアレクサンドラを憎んでいた。その気持ちはアレクサンドラも同じだったようで、ラスプーチンの死をミハイロヴィチに責任があると非難した。
アレクサンダー・コツィビンスキー、オルランド・フィゲス、マルガリータ・ネリパの3人の優れた歴史家がこの考えを展開し、ミハイロヴィチが陰謀家たちと頻繁に会っていたこと、彼に対する尊敬の念が強かったことを指摘している。おそらく彼はユスポフに行動を促し、何らかの助言をしたのだろう。しかし、ニコライの伝記を書いたジェイミー・コックフィールドは、彼が陰謀の首謀者だという説を否定する。もし彼がラスプーチンの死の背後にいたとしたら、それを秘密にしておくことはありえないだろう。ニコライは殺人が起こるまでそのことを知らなかったし、彼が日記に記録した内容も誤りがあった。ミハイロヴィチが殺人の首謀者であることを示唆する状況証拠さえない。
結局、膨大な証拠から、フェリックス・ユスポフがこの計画を立案し、実行に移した人物であることが判明した。彼の率直な手記は、他の共謀者たちによって裏付けされた。確かにこれらの証言には矛盾があるが、犯罪の専門家は、それを想定しているのである。暗殺が不器用に行われたことは、それが素人の仕事であったことを示している。ユスポフ氏のやり方には、独特の素朴さがあった。彼は明らかに陰謀を喜び、その神秘的な秘密に胸をときめかせていた。ユスポフは、ロシアの救世主として国民から喝采を浴びる瞬間を、想像の中で楽しんでいた。殺人は、この王子の性格にそぐわないものであったから、彼の動機が愛国的であったことは、不承不承ながら受け入れざるを得ない。
ユスポフは計画をまとめるにあたり、まずラスプーチンの長年の敵である議会のミハイル・ロジャンコのもとを訪ねた。ユスポフは行動計画を打ち出すことで、ロジャンコの計略を呼び起こし、ロシアで最も太った男が騒がしいだけであることがすぐに明らかになった。ロジャンコは、たとえ標的が不倶戴天の敵であっても、何もしないことの理由を突然思い出した。次にユスポフが注目したのは、自由党カデットの党首で下院議員のワシリー・マクラコフであった。この革命家はテロリストでもあるのだから、喜んで農民を殺すだろう。マクラコフは唖然とし、気分を害した。
「私が暗殺のために事務所を構えているとでも思っているのか」と。マクラコフは政治的な反論も展開した。ラスプーチンは帝政の信頼性を破壊していた帝政が崩壊すれば、彼が要求しているような民主的な政府がその灰の中から生まれるだろう。ラスプーチンはこの革命を実際に促進していたのだから殺すべきではない。殺しても、皇后はすぐにラスプーチンの代わりとなる者を見つけるだろう。
ユスポフはマクラコフをたしなめた。王子は、この優れた弁護士が、アレクサンドラがラスプーチンの後釜になれると考えているのは、彼の「超自然的な力」を認めていないからだと指摘したのである。「しかし、私はオカルトに携わっているので、真実を知っている」とユスポフは続けた。「ラスプーチンは100年に一度の力を持っていると断言できる. . . もしラスプーチンが今日殺されたら、皇后は2週間以内に精神病院に収容されるだろう。彼女の精神の均衡は完全にラスプーチンに依存している。彼女はラスプーチンが失脚するやいなや崩れ落ちてしまうだろう。 もし皇帝がラスプーチンとその妻の影響から解放されればすべてが変わるはずだ。彼は良い立憲君主になれる」。
その後、ユスポフは何度もマクラコフを訪ねた。陰謀に関係のない人も相談相手として使う必要があった。ユスポフは不安でもあった。自分の首を賭けるつもりだが、バレないようにしたいとも思っていた。マクラコフは、ラスプーチンを殺して自動車事故に見せかけることを提案したが、ユスポフは、それはあまりにも複雑な話だと思った。
マクラコフに武器について尋ねると、農民を殴るためのゴム引きのダンベルを手渡した。ユスポフは、ラスプーチンを殴り殺すという考えに恐怖を感じながらも、その武器を受け取った。その後、マクラコフは否定したが、ユスポフは彼から青酸カリの結晶も1箱もらったと主張している。
ユスポフが心の支えとしたのは、ドミトリー・パブロビッチ大公であった。ニコライ2世のいとこである。パブロビッチの父は妻を亡くし、莫大な財産をつぎ込んでロシアから追放された。ニコライとアレクサンドラは、パブロビッチを養子のように可愛がり、一緒に過ごすようになった。ニコライは、パブロビッチが長女オルガと結婚するか、自分の亡き後はパブロビッチに王位が移るよう、継承法の改正を画策しているなどと噂されることもあった。アレクサンドラと農民の「友人」がロシアを破壊しているという確信から、パブロビッチがラスプーチンに打撃を与えることに同意したのも無理からぬことであった。
ユスポフとパブロビッチは、同性愛の関係だったのだろうか。ユスポフは確かにパブロビッチへの憧れを抱いており、二人は恋人同士だったのではないかと疑う人もいた。皇后は、パブロビッチがユスポフと交際し、彼女が「狂っている」と呼ぶ人たちと一緒に行動していることに気をもんでいた。パブロビッチがゲイであったという証拠はないが、ユスポフを友人として愛していたことは確かである。二人の友情を考えれば、ユスポフがこの若い男を陰謀に引き込むのは自然なことだった。また、この計画には稀に見る戦略的な先見性があった。大公であるパブロビッチは訴追を免れ、皇帝だけが彼を罰することができるのだ。パブロビッチは後にユスポフに、「もし私がこの事件に加わっていなかったら、あなたは政治犯として絞首刑にされていたでしょう」と書き送っている。
パブロビッチは、”王政の救済のために、真の君主主義者によって殺人が行われるべきだ “と考えていた。ユスポフが11月に勧誘したもう一人の男はウラジミール・プリシュケビッチで、彼は確かに「真の君主論者」であった。1870年にベッサラビアで生まれたプリシュケヴィチは、ロシアにとって議会は異質なものであると考え、議会を弱体化させる目的で議員に当選した。プリシュケヴィチはラスプーチンを軽蔑しており、1916年11月19日には「すべての悪はあの闇の力、ラスプーチンが率いる影響から生じている」と激しい演説を行った。彼は皇帝の無能で腐敗している大臣たちを「眠れる12人の美女」と呼んだ。ロシアを救うためには、彼らは目を覚まして行動を起こさなければならない。”大臣たちが自分のキャリアよりも 任務を優先するならば…彼らは皇帝のもとへ行き 身を投げ出し、恐ろしい現実に目を覚ましてくれるよう 頼まなければならない”。
この言葉に議場は歓声に包まれた。ユスポフはギャラリーでプリシュケヴィチがラスプーチンを糾弾するのを聞いていた。彼は青ざめ、震え、まるで「抑えきれない感情」に打ちひしがれているようだったという。翌日、ユスポフはプリシュケーヴィチを訪ねた。彼は演説を褒め称えたが、何の変化もないのではという危惧を口にした。ユスポフはラスプーチンの殺害を提案した。プリシュケヴィチは、自分も一度は考えたことがあると言い、ユスポフの陰謀に加わることにした。
翌日の晩、モイカ宮殿に到着したプリシュケビッチは、ドミトリー・パブロビッチと第4の共謀者、セルゲイ・スコーチン(精鋭歩兵連隊の29歳の中尉)に紹介を受けた。スコーチンは、王子の一族がツァールスコエ・セローで経営していた病院で療養中にユスポフに出会ったらしい。このため、スコーチンがユスポフの性的にパートナーだったのではと疑われることもある。しかし、スコーチンが陰謀論に傾倒していたのは事実である。彼は、ラスプーチンとアンナ・ヴィルボヴァはドイツのスパイであり、彼らを排除することがロシアを救うことになると信じていた。スコーチンの仕事は死体を処理することだったらしいが、それは彼の貴族の同僚たちの威厳に反する仕事であった。プリシュケビッチは、この陰謀に5人目の男を引き入れた。
スタニスワフ・ラゾヴェルトは、フランスで教育を受けたポーランド人医師で、戦争が始まって2日目にロシア軍に入隊した。ラゾヴェルトは、プリシュケビッチの医療組織と前線での作戦を指揮した。彼は3度の負傷を経験し、聖ゲオルギオス十字勲章を授与されている。
共謀者たちはラスプーチンをアパートから誘い出し、一日中彼を尾行している警備員から誘い出すことを計画した。ラスプーチンの敵はモイカ宮殿でラスプーチンを殺すだろう。そのためユスポフはラスプーチンと親しくならざるを得なかったが、王子はそのことに嫌悪感を抱いた。そこでユスポフは、1916年11月20日、共通の友人のアパートでラスプーチンに会うことにした。
ユスポフは、ラスプーチンのあまりの変わりように驚いた。彼はもはや「平凡な農民のコート」は着ておらず、淡いブルーの絹のブラウスと袖口の広いベルベットのズボンを身に着けていた。王子は体調が悪く、ラスプーチンの治癒能力を必要としていると主張した。ユスポフは農民の虚栄心をあおり、最高の医者も自分を助けることができなかったと告げた。「私があなたを治してあげよう」とラスプーチンは大胆に答えた。「医者?彼らは何も知らないんだ。何でもいいから薬を詰め込むだけだ。そして君はさらに悪くなる。でも私はもっといい方法を知っていますよ」 ラスプーチンはユスポフを自分のアパートに招待した「癒しのセッション」のためだ。ユスポフは続けた:
霊能者は私をソファに寝かせた。立ったまま、私の目をじっと見つめ、胸、首、頭を撫で始めた。突然、彼はひざまずき、そして、私の眉間に手を当てて祈り始めたようだった。彼は頭を低くして、顔が見えないほどだった。彼はしばらくその姿勢のままだった。それから突然飛び上がり、[私の体の上を両手で]通り過ぎ始めた。彼はある種の催眠術のテクニックに精通しているようだった。彼の催眠術の力は絶大であった。私はそれに支配され、全身に暖かさを吹き込まれているのを感じた。私はしびれを覚え、体が麻痺しているようだった。私は言葉を出そうとしたが、舌が従わず、まるで強い麻薬が効いているように、眠りに落ちそうであった。ラスプーチンの目は燐光のように輝き、私の目の前を照らしていた。
ユスポフは魔力を解くのに苦労し、ラスプーチンは状況をコントロールできなくなったことを察知して、セッションの終了を明るく告げた。しかし、彼は王子に、またすぐに戻ってくることを約束させた。
ラスプーチンとユスポフはペトログラードのレストランやナイトスポットを一緒に訪れるようになった。社会はこの関係にざわめいたが、マリア・ラスプーチンが後に示唆したように、ユスポフがラスプーチンを性的魅力に感じていたと考える理由はどこにもない。ユスポフの決意が揺らぐこともあったが、12月第1週のある出来事が彼に行動を起こさせることになった。12月3日、大公妃エリザヴェータはツァールスコエ・セローでのアレクサンドラとの嵐のような会談の後、急いでジナイダ・ユスポフにラスプーチンに対する強固で不屈の決意を告げた。”彼女は私を犬のように追い払った!” エリザヴェータは泣いた。アレクサンドラは以前、ラスプーチンを批判したユスポフの母ジナイダを辱め、別れ際に「二度と会わないことを望むわ」と宣言していたのだ。
ユスポフの母親と大公妃エリザヴェータは、ユスポフの人生で最も影響力のある人物で、二人ともラスプーチンをめぐって皇后と対立していたのである。エリザヴェータはこの状況に絶望したが、ジナイダは、後に認めたように「憎しみで息が詰まる」「これ以上耐えられない」と思っていた。二人ともユスポフの計画を知っていて、行動を起こすように勧めた。ジナイダは、息子に宛てた手紙の中で、「平和的手段では何も変わらない」と書いている。母やエリザヴェータに恥をかかされたことで、ユスポフの迷いはようやく消えた。
その計画は、ユスポフがラスプーチンをモイカ宮殿に招待することであった。そこで人の目につかない所でラスプーチンは毒殺される。陰謀者たちは彼の体を袋に詰め、リトル・ネバ川に投げ込み、その強い潮流でフィンランド湾に運ぶというものだった。運が良ければ、ラスプーチンは消えてしまう。死体がなければ、誰もラスプーチンの罪を問うことはできない。少なくとも、それは彼らが共有する広範な誤算であった。パブロビッチのスケジュールは決まっていた。疑惑を持たれないように予定をキャンセルすることはできず、次に空いている夜は12月16日(金)だった。そして、この日取りが決まり、共謀者たちは最終準備に取り掛かった。
フェリックス・ユスポフ王子は、12月16日が近づくにつれ、道徳的な不安を感じるようになった。彼は、友好と歓待を受けた人を殺すのは間違っていると知っていた。紳士はそんなことはしない。このジレンマを解消するために、ユスポフはカザン聖母大聖堂に行き、何時間も祈り続けたという。そして、宗教的な高揚感に包まれながら、その姿を現した。ユスポフはロシアを、そしてニコライ2世とその家族を救おうとしていたのだ。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』20
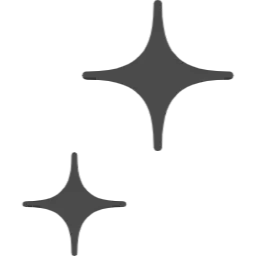
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

