たそがれ時にやってくる影
ラスプーチンは第一次世界大戦中、アルコール依存症で酒を飲み続けていた。これは、キオニヤ・グセバの攻撃の後、彼が恒常的な痛みを抱えていたためである。また、その2年前から苦しんでいた精神的危機からも来ていた。ラスプーチンはその葛藤を解決することができず、それが何であるか定かでないほど困惑していた。祈りが通じないと感じると、1897年にヴェルコトリェで改宗する前と同じように、アルコールに手を出した。マリアが父にアルコールの使用について話そうとすると、彼は防衛的になった。「どうして飲んではいけないのだ?私は他の人たちと同じように人間ではないか?」
ラスプーチンの日課は決まっていた。朝起きるのは遅かった。夜遅くまで起きているのだから、当然といえば当然である。朝食を食べた後、アンナ・ヴィルボヴァに電話をかけ、ツァールスコエ・セローの最新状況を知った。彼らは夜明け前から活動していたが、ラスプーチンと過ごす時間がどんどん少なくなっていった。ラスプーチンは、朝11時から午後1時まで書斎にこもり、人々の訪問を受けた。昼食後、昼寝をしたり、風呂に入ったりしていた。
ラスプーチンの夜は、彼の年齢の半分の男でもひどく疲れさせるようなものだった。彼は友人を訪ね、首都で最もファッショナブルなレストランやホテルでのパーティーに出席した。モイカ運河沿いのドノンレストランやホテルアストリア、ホテルロシア、ホテルヨーロッパの常連であり、とりわけジプシークラブの雰囲気を楽しんでいた。マザルスキー・ジプシー・コーラスやヴィラ・ローデで夜通し飲み食いし、歌い、踊っていた。
ホテルアストリアのフランス料理店の支配人ジョセフ・ヴェッキは、戦争中のある夜、ラスプーチンを讃えるパーティを担当したときのことを書き残している。ヴェッキは、王女と12人の優雅な身なりの女性たち(中には幼い娘もいた)が到着し、個室に入っていくのを見た。ヴェッキはラスプーチンの「汚い」「不潔な」ひげ、そして「恐ろしい鳥のくちばしのような鉤鼻」に衝撃を受けた。ラスプーチンの額には髪の毛が束で落ちており、手は「不潔で、噛まれて黒くなった爪がある」状態であった。彼のオーラは「邪悪で汚らわしい」ものだった。ヴェッキの印象は否定的だったが、彼はラスプーチンが「他の人とは異質」であっても「疑いようのない力を持っている」ことを理解した。ラスプーチンが食卓につく姿は「気持ち悪い」ものだった。「ナイフとフォークの代わりに、獣のように爪のような長い指を使って、皿の上の食べ物をつかみ、下品に詰め込むように食べていた」という。ラスプーチンは食事の間中、酒を飲んでいたが、決して酔っぱらっているようには見えなかった。彼は「主人や婦人たちの前では最も下品な言葉」を使った。夜中の3時過ぎにラスプーチンは待機していた車に乗り込み、婦人たちは「ラスプーチンと関わらないように」反対方向に出発した。
アルコールはラスプーチンの夜を盛り上げ、警察の報告書はそれが彼にどのような影響を与えたかを記述している。1915年11月14日、彼は女性の仲間と「とても酔っぱらって」自分のアパートに戻ってきた。「彼らはまたすぐに出て行った」、そして彼は夜中の2時に一人で現れ、「完全に酒に酔った」のである。11月25日、「ラスプーチンは午前5時に帰宅した」。12月3日、彼は女優のヴェラ・ヴァルヴァロヴァと一夜を過ごし、翌日完全に酔っぱらって自分のアパートに戻ってきた。12月7日、彼はドノンで食事をし、ホテル・ロシアで2人の女性と一緒になった後、ヴァルヴァロワと夜を過ごすために出た。2日後、ラスプーチンは夜中の2時に2人の女性を誘った。ラスプーチンが扉を叩いてベルを引いても、ヴィラ・ローデが閉まっていて入れなかった。一行はマサルスキーのジプシーコーラスにたどり着き、そこで朝の10時まで過ごした。その後、まだ酔っぱらっていた彼らは友人のアパートに移動し、その日はそこで過ごした。ラスプーチンの護衛は、彼らの担当者の状態を分類する専門用語を開発した。彼らの報告書は、彼を “少し酩酊”、”酩酊”、”かなり酩酊”、”泥酔”、”かなり泥酔”、”完全に泥酔”、”死にそうに泥酔”、最後に “完全に酒に溺れる “と描写している。
1915年5月14日の夜10時に、ラスプーチンは女性を誘惑した後に、2人の男に追われて住宅から逃げ出すのが目撃されている。6月2日、ラスプーチンは家に戻り、住人である3人の女性に酔って言い寄った。彼は門番の妻にキスしようとしたが、メイドのドゥーニャが引き離した。ある朝、二人の女性が彼の部屋を出てきて、彼を「農民のクズ」と大声で呼び、「シャツ一枚でヴィラ・ローデを走り回っているのを見たことがある」と警察に告げた。1916年1月14日の朝、ラスプーチンは自分の建物の入り口のドアの大きなガラスを割った。4日後、彼は朝7時に「完全に酔っぱらって」戻ってきた。「通りで大声で歌った」後、午前中は自分のアパートで「叫び、足を踏み鳴らし」て過ごした。
ラスプーチンは酔った姿を皇后に見せることはなかったが、二日酔いで震えた状態でツァールスコエ・セローに出廷させられたこともあった。アレクサンドル宮殿に来るようにという電話がかかってきたこともあった。その時、訪ねてきた友人たちは、「そんな姿を皇后に見られたら、すべてが台無しになる」と忠告した。彼らは列車に乗る前に仮眠を取るよう彼を説得した。彼らは首を横に振りながら「うちの霊的指導者は最近、あまりにも自分を甘やかしすぎている」とささやいた。またある時、ラスプーチンは酔っ払ってツァールスコエ・セロー駅にいた。彼はホームでよろめき、彼の行動を監視していた内務省警察部大佐のコミサロフがかろうじて転倒を免れさせた。ラスプーチンは、世間知らずの警官でさえショックを受けるような言葉で、アレクサンドラのことを言い始めた。コミサロフはラスプーチンを揺さぶり、皇室についてそのような言い方をするのはやめようとはっきり言った。
セックスはラスプーチンの人生において重要な部分を占めていた。彼は助けを求めてきた女性たちにしばしばセックスを要求した。多くの人が彼の抱擁から逃げ出した。 ある女性は階段の途中でラスプーチンのメイドに戻るようと頼まれた。 “彼は孤独を感じている”と。 ある兵士の妻は夫を病院に入院させて 戦線に戻さないようにと願い出た。 ラスプーチンは彼女の服を脱がせ、胸を揉み、キスをするように求めた。彼女は彼の要求に従ったが、ラスプーチンは翌日また来るように言った。彼女はもう戻ってこなかったらしい。
ラスプーチンは、同じ建物に住むカーチャという18歳の仕立屋に明らかに夢中になっていた。警察は、彼がいつも彼女に会いたいと言い、酔っぱらってドアをノックし、彼女が自分のアパートを訪れれば50ルーブルを差し出したことを記録している。彼は女優のヴァルヴァロヴァと長い間関係を持ち、先に述べたように、彼らはしばしば夜を共にした。ラスプーチンはヴェーラ・トレグボヴァという名の娼婦と定期的に会っていた。彼の有償の密通には、スムーズにいかないものもあった。ラスプーチンは使用人が介入するまで、一日中自分の寝室に娼婦を閉じ込めていたこともある。
アレクシス・フィリッポフはジャーナリストであり、1911年に『ラスプーチンの思考と瞑想』を出版した友人である。彼とラスプーチンは多くの時間を共に過ごし、様々なことを話した。フィリッポフはしばしばラスプーチンに女性についての議論をふっかけようとしたが、ラスプーチンはいつもはぐらかされた。フィリッポフは「誰かが多少なりとも性的なテーマを取り上げると、ラスプーチンはすぐに遊び半分でその話題を変えてしまう」ことに驚いた。ラスプーチンはまた、反ユダヤ的な冗談や話題は気にしないことを明言していた。
フィリッポフとラスプーチンはよく一緒に風呂にいった。彼は友人の裸体についての記述を残している。ラスプーチンと衛生に関して、他の人が言っていることと矛盾していることをフィリッポフは書いている。この点でもラスプーチンは謎であった。「ラスプーチンは並外れて清潔で、よく下着を取り替え、風呂に行き、決して臭くなかった」とフィリッポフは1917年に証言している。「彼の身体は非常にしっかりしており、贅肉がなく、赤みがあり、均整がとれていて、その年齢によくある腹筋や弛緩した肉がなく、・・・ある年齢で黒や茶色の色合いを帯びる性器の色も濃くなっていない」。フィリッポフが指摘した「身体的特異点」はこれだけである。ラスプーチンの伝説に登場する「巨大な性器」については何も言っていない。ラジンスキーの言葉を借りれば、ラスプーチンは「若く見える体を持った非常に清潔な農民であった、それだけである」。
1912年1月23日、警察は新たに体系立ててラスプーチンの警備を開始した。捜査官はこの農民の一挙手一投足を追跡し、その報告書から彼の生活の公的側面を明らかにするようになった。例えば、ラスプーチンの日常生活における娼婦の重要性を知ることができる。「彼はめったに一人で街の通りに出ることはない。しかし、そんな時は娼婦の集まる通りに行き、一人を選び、ホテルや浴場に連れて行くのだ 」とある。また、”ヘイマーケット広場で売春婦を雇った “という話もある。他にも “ネフスキー通りで娼婦ペトロブナを雇い 一緒に浴場に行った” “ポリツィスキー橋の近くで雇った娼婦とコンユシェヌィ通りの風呂に行った” “彼は娼婦アンナ・ペトロブナともその風呂へ行った” ラジンスキーはこの種の警察の証言を19件も引用している。
ラスプーチンは一日に何人もの娼婦を雇うこともあった。ある報告では、「彼は素性の知れない娼婦と二度風呂に行った」とある。別の報告書では、娼婦とホテルに行き、「20分ほど滞在した」とある。別の報告書では、彼はジナイダ・マンシュテットという信奉者で非常に立派な女性と1時間半過ごした後、「知らない女性、おそらく売春婦を訪ね、20分後に再び出てきた」と書いてある。マリア・サゾノワと2時間過ごした後、彼は「娼婦を雇って彼女のアパートに行き、そこからまたすぐに出てきた」のだそうだ。どうやら「善良な」女性と「堕落した」女性のコントラストが、ラスプーチンに何らかの活力を与えていたようだ。社交界の女性たちとの時間が長く、他の女性たちとの時間が短いという違いも大きかったかもしれない。
ラスプーチンの性生活は複雑で、私たちはそれを完全に理解することはできないかもしれない。彼の行動から、常にセックスを求めていたと思われがちだが、そうではなかったかもしれない。ラスプーチンを知っている売春婦の少なくとも一人は、彼がインポテンツであると思っていた。2つの事例では、ラスプーチンと彼が雇った女性に何が起こったかがわかっている。そのひとつは、ドアを閉めた後、ある警察の報告書の言葉を借りれば、それは「最も奇妙」であった。「ラスプーチンは(娼婦に)ビールを2本買ってやり、自分では飲まなかった。彼女に服を脱ぐように頼み、彼女の体を見ただけで立ち去った」。もう一つは、この頃、ラスプーチンの常連客だった娼婦の話である。彼女はピーチという名前で、ラジンスキーが70年代にインタビューした時には、もう老婆になっていた。
初めてラスプーチンに雇われたとき、ピーチは17歳で、ぴったりとしたコートを着ていた。彼は彼女に大金を約束した。彼女は、農民がどこでそんな大金を手に入れるのかと不思議で、たぶん、誰かを殺したのだろうと思った。彼女の考えを読んだかのように、彼は言った「愚か者め!私が誰だか知らないのか?私はラスプーチンだ」。彼は彼女を安ホテルに連れて行き、座って彼女が服を脱ぐのを黙って見ていた。彼の顔は突然、血の気が引いたように白くなった。このとき、ピーチはかなり怖くなった。
娼婦たちとの出会いは、セックスが目的でないこともあった。ラスプーチンの挑戦は、性的衝動に抵抗すること、つまり、誘惑と衝動に直面することによって肉欲を超越することであった。彼は宗教的な経験を得るために娼婦たちを雇っていたのである。
1912年の警察の報告書には、興味深い内容が書かれている。ある刑事は、”ロシア人(ラスプーチンのコードネーム)は、一人で歩いているとき、独り言を言い、腕を振り、体を叩いて、それによって通行人の注意を引いている “と記している。ラスプーチンは自分自身に語りかけていたのか?それともサタンを叱責していたのだろうか?
妻のプラスコバヤは、夫と他の女性との関係を黙って受け入れていた。実際、ラスプーチンの家庭生活は、父エフィムとの関係を除けば、幸せだったようである。この親子関係は決して楽なものではなく、警察はポクロフスコエでエフィムの本心を表すひどい乱闘騒ぎを目撃している。二人とも「ひどく酔って」おり、父親が「最も汚い言葉」で息子を罵り始めたのである。ラスプーチンは激怒し、椅子から飛び降り、父親を家の外に放り出し、地面に叩きつけて殴りはじめた。「俺を殴るな、この悪党!」 と、エフィムは叫んだ。警察が二人を引き離すのに苦労した。ラスプーチンは父親を激しく殴り、エフィムの片方の目は腫れ上がった。これが引き金となり、エフィムは殴り返し、息子の腰に怪我を負わせた。
1916年にエフィムが死んだとき、ラスプーチンは首都にいた。ラスプーチンは葬儀のためにポクロブスコエに戻ると言っていたが、そうしなかった。ベレツキーに、皇室が彼を首都で必要としているとほのめかしたのだ。警察本部長はラスプーチンが「近親者を失った者にとって最初の数日はとても鋭敏であるため、生活様式を変えるだろう」と予想した。しかし、ラスプーチンは父を悼んだとしても、それを隠していた。 彼の普段の振る舞いは続いていた。ベレツキーは「すべてが同じであった」と指摘した「同じように酔っぱらい、同じく酒盛り、同じく女性との関係」。
ラスプーチンとその息子もまた、遠い関係であった。荒れたり困難な関係ではなかったようだが、ドミトリーは根っからの農民で、ラスプーチンは都会での生活の利点を押しつけることはしなかった。ドミトリーはポクロフスコエの村の学校で初歩的な教育を受けただけだった。1915年秋、ドミトリーが徴兵されると、ラスプーチンは慌てた。プラスコバヤは、「もう息子に会えないのでは」と思ったという。
アレクサンドラはニコライに「我が友は、彼の息子が戦争に行かなければならないことで絶望しています」と手紙で知らせた。皇帝はドミトリーを兵役から免除することもできたし、ラスプーチンもそれを望んでいた。ラスプーチンは「彼の惨めで弱々しい子」が前線で生き残ることを、ほとんど信じていなかったのである。しかしニコライ2世は、戦場で倒れる者もいる中で彼の家族を助けることを拒否し、ドミトリー・ラスプーチンにもそのような便宜を図ることはなかった。
しかし、皇帝夫妻は冷淡ではなかった。皇后は、この青年が戦場に出ることはないだろうと考えていた。アレクサンドラは彼を自分の病院の列車に医療看護師として配属させた。息子は父と同じようにツァールスコエ・セローにいたのだろう、会う人こそ違っていたが。ドミトリーは、職務上の呼びかけに従うという性格の持ち主であった。イギリス人の評論家は、このロシア史の瞬間について、「『病気だ』と報告する兵士の数は膨大だった」と書いている。「前線から逃げるには、どんな言い訳でもよかった。彼らは、いつも負けてばかりで、戦う意味がないと言っていた」。
ラスプーチン夫妻がドミトリーの運命について悩んでいる間、皇后は「あまりに灰色でとても悲しくなりました」と書いている。「しかし、今、太陽が雲を突き破ろうとしています。木々の色はとても美しく、多くが黄色や赤、銅色に染まっています。夏が終わり、果てしない冬が待っていると思うと悲しい」。
ラスプーチンは1916年8月、巡礼の旅に出ることにした。帝国内のどこへでも豪華に旅することができたが、彼は1897年に改宗した場所であるヴェルホトゥーリエを選んだ。修道院を目指したとき、おそらく彼はこれが最後の訪問になるとは思ってもみなかっただろう。
10歳の少女タマラ・シシュキナも、たまたまヴェルホトゥーリエに行く途中だった。ラスプーチンが乗っているという噂が広まり、満員の車内が興奮に包まれたことを、数年経った今でも彼女は覚えている。ラスプーチンは他の乗客から見えないように一人で降り、他の乗客は待つことを余儀なくされた。ラスプーチンは修道院の名誉ある訪問者だった。シシュキナは、教会のドアの前に「皇帝にふさわしい豪華な赤い絨毯」が敷かれていることに注目した。最後の皇帝のお気に入りには、何も良すぎるということはなかったのだ。
キャンドルやシャンデリアから差し込む光が、銀の聖像カバーや聖シメオンの聖遺物を納めた金の石棺に反射している。ラスプーチンは礼拝堂の真ん中に敷かれたラグの上に立っていた。彼の髪は後ろでまっすぐに櫛で梳かれ結ばれていた。大きな房のついた帯を鮮やかな黄色のルバシカに合わせ、ベルベットのゆったりとしたズボンと漆塗りのブーツを履いていた。ラスプーチンは熱心に祈り、大きく体を交差させた。シシュキナは「彼の顔は平和で、集中していて、優しかった」と回想している。
十字架はついに祭壇から取り出され、満員の会場の真ん中に置かれ、人々が来てこれを崇拝するように招かれた。ラスプーチンが最初に十字架に接吻し、その後に彼の側近が続いた。ラスプーチンに近づきたい、ラスプーチンに触れたい、十字架にたどり着きたいと、突然、殺到した。「私はラスプーチンの右手の真下に投げ出され、彼は私の上で十字架のサインをした」。
シシュキナがヴェルホトゥーリエで過ごした3日間は、忘れられないものとなった。彼女の頭の中は、「教会での厳粛な典礼」と、修道院のいたるところでラスプーチンを迎えた「騒々しい集まり」の記憶でいっぱいであった。彼とその一行が去った後、他の巡礼者たちは「騒がしい小さなグループ」ごとに集まり、悪名高いグレゴリー・ラスプーチンとの出会いを語り合った。
このような友好的な姿勢を共有できるロシア人はほとんどいなかった。「皇后と僧侶の猥褻なパンフレット」が1916年末にペトログラードで、もちろん違法に、出回り始めた。映画館では、ラスプーチンがアレクサンドラやその娘たちと親密なポーズをとっている「嫌な捏造映像」が上映された。また、ラスプーチンをニコライとアレクサンドラを操る人形師として描いた漫画も登場した。
ラスプーチンに対するロシア人の怒りは1916年の秋に頂点に達した。レストラン経営者のジョセフ・ヴェッキは、ラスプーチンを「ハゲタカ」と表現し、その「翼はロシア全土に影を落としていた」と述べた。人々は彼が「国の実質的な支配者である」と信じ、反逆罪の非難は必然的に皇后にも向けられた。ポール・ミリュコーフは、ロシアを脅かす「暗黒の力」に対して議会で激論を展開した。このリベラルな歴史家・政治家は、史上最も影響力のある演説の1つとなったが、戦争に絡むロシアの腐敗と無能さのひどい例を挙げ、その都度「これは愚かさか、それとも反逆か」と修辞的に問いかけている。しかし、「ラスプーチンの影響力の噂は、革命のプロパガンダをすべて合わせたものよりずっと効果的に君主制の原則を損なっている」と考える者もいたのである。
反対運動は容赦なく、ラスプーチンを震撼させた。彼はアレクサンドラに言った。”サタンは新聞で恐怖を広める” “何も良いことはない” 。フィリッポフはラスプーチンを擁護する唯一のジャーナリストだった。彼は6枚のパンフレットで友人のために発言したが、世論を曲げることはほとんどできなかった。『シベリア貿易新聞』は、ラスプーチンが若いころ馬泥棒をしていたと告発し、明らかに神経を逆なでした。ラスプーチンは編集者に電報を打った。「新聞に掲載されているように、私がいつ、どこで、誰から馬を盗んだか教えてくれ。どこからの情報だ?3日後に返事を待つ。もし、返事がなければ、誰に文句を言えばいいのか、何を言えばいいのか、私にはわかっている」。編集者はこの通信を、ラスプーチンを半端な教育を受けた農民と呼ぶ軽妙な解説とともに掲載した。しかし、撤回されることはなかった。
ラスプーチンは戦争中、何度も脅迫や暴行を受けた。ある夜、ラスプーチンがヴィラ・ローデで皇后を侮辱するような発言をすると、激怒した将校がラスプーチンを殴った。3人の将校が彼に襲いかかり、同様の軽率な行動で病院送りにした。ある晩、ラスプーチンは銃声でパーティーから逃げざるを得なくなった。客の何人かが自分を殺そうとしたことを知ると、ラスプーチンは青ざめ、目に見えて老け込んだように見えた。ある夜、ネフスキー広場の馬車がラスプーチンを轢きそうになり、またある時は車が彼のそりに突っ込み、彼はあざだらけになった。ある日の午後には、ラスプーチンの乗った車の前に材木の山が転がり込んできた。その男は、イリオドールのかつての権力基盤の地であったツァリーツィンの農民であった。
これらの「事件」のいくつかは噂や誇張であったかもしれないが、多くの人がラスプーチンを憎み、彼の命が危険にさらされているというメッセージは明らかであった。彼はこれに対して、自分の警備を強化するよう求めた。「間違いなく、私は殺される!」と言った。「彼らは私たち全員を殺すだろう、パパとママも殺される」。
ラスプーチンは、匿名の、あるいは “復讐者 “のような脅迫的な名前で署名された手紙を受け取った。「我が祖国は危機に瀕している」と書かれたものだった。「不名誉な和平を結ぼうという話もある。この暗号電報を受け取ったということは、あなた方の影響力が大きいということです。そこで我々選ばれし者は、人民が責任を負うべき大臣を与え、国家議会を召集し、わが国が破滅から救われるよう、問題を解決することを求めます。命令に従わない場合、我々はあなたを殺すだろう。慈悲はかけられない。我々の手はグセバの手のように縮むことはない。どこへ行こうとも死はつきまとう。賽は投げられたのだ」。
「奴らは私を暗殺しようと考えている」1916年初め、ラスプーチンは刑事にそう告げた。彼は疲れ、落ち込んでいた。彼を遠くから賞賛していたおしゃれな女流作家テフィは、「彼が使いこなそうとした(そして失敗した)力が、彼を足元から押し流し、連れ去っていく」と考えていた。ある女性フォロワーは、彼のアパートの雰囲気が「だんだん緊張してきた」と回想している。「 表面上は同じように訪問が行われていて、電話がひっきりなしに鳴っていた。あらゆる年齢の女性が、顔色が悪く、マスカラをして、お菓子や花を山ほど持って、いろいろな箱が散乱している中を行ったり来たりしていた。ラスプーチン自身は疲れていた。彼は何か探すようにあたりを見回し、しばしば疲れ果てた狼のように見えた。日課は彼の生活を多忙で不安定なものにした。すべてが即興的で不安定に見え、まるであの暗くて人を寄せ付けない建物の上に何らかの打撃が迫っているようだった」。ラスプーチンは運命論者であった。「私がもうすぐ終わりが来ることを知らないと思っているのか?」と彼は尋ねた。
冬の雪がペトログラードに降り積もり、疲弊し幻滅した都市を白一色に包んでいた。1916年12月2日、ラスプーチンは皇帝夫妻に会うようにとの召集令状を受け取った。彼はその日を訪問の準備に費やした。酒には手をつけず、浴場に行き、教会に行ってからツァールスコエ・セロー行きの列車に乗り込んだ。雪が降る中、待機していた自動車でヴィルボヴァのレモン色の家へ向かう。すでに皇太子夫妻は到着しており、旧友たちはいつものようにお茶を飲んだ。出発のとき、ラスプーチンは緊張していた。ニコライはラスプーチンに恒例の祝福を求めた。ラスプーチンは静かに答えた 「今回は、あなたが私に祝福してください」と。2週間もしないうちに、ラスプーチンは死んでしまった。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』19
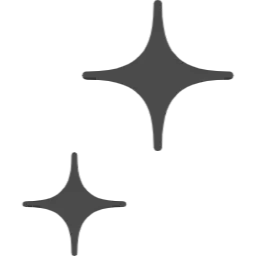
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

