スピリチャルな危機
1913年2月21日朝、ペトロパヴロフスク要塞から21の礼砲が鳴り響き、ロマノフ王朝300年の祝典が幕を開けた。ニコライ2世は詔書の中で、「我らと愛する国民に対する神の加護が、現状よりも乏しくならないように」と祈っている。ラスプーチンの悪名で王位の威信が失墜したのは確かである。しかし、ニコライは希望を持っていた。「全能の神がロシアの地を強化し、栄光を与え、祖国の栄光の旗を高く掲げ、安定させる力を我らに与えてくださるように」。
ニコライはその日の朝、家族を率いて冬宮からカザン聖母大聖堂まで行進した。正午にはテ・デウム(聖歌)が予定されていた。ロジャンコは、議会議員に教会の後方の席が割り当てられていることを知り、土壇場で騒ぎを起こした。ロジャンコは同僚のためにもっと目立つ場所を確保したが、その場所に「農民服を着て胸章をつけた知らない男」が座っていて、動こうとしないことを知った。「案の定、ラスプーチンだった」とロジャンコは回想した。その農夫に立ち去るように命じたが、ラスプーチンは動かず、まるで催眠術をかけるかのように、太った大統領の顔を強烈に見つめた。ロジャンコは「ものすごい力」が襲ってくるのを感じたが、ようやく自分をコントロールできるようになり、ラスプーチンに立ち去るよう命じた。「私はあなたよりもっと偉い人の希望でここに招かれたんだ!」。ラスプーチンは反論しながら招待状を見せた。ロジャンコが威嚇するように彼の周りをうろつくと、ラスプーチンはひざまづき、「ああ、主よ、彼の罪をお赦しください」と叫んだ。ロジャンコは衛兵を呼び寄せた。敗北を確認したラスプーチンは大理石の床から立ち上がり、大統領に最後の怒りの視線を送ると、堂々と聖堂を出て行った。
対立の余波は、皇族の到着時にもまだ教会に波及していた。聖堂に向かう行列は、あまり盛り上がらない。教会にいる貴族や役人たちは、長い通路を歩くニコライとアレクサンドラに厳しい目を向けている。皇帝は没頭しているようで、妻は不安と緊張がみられる。春になると、帝国全土でさまざまな出来事が起こり、100周年記念式典は不安定なスタートを切った。好奇心は、忠誠心や善意よりも明白だった。
ウラジーミル・ココフツォフ首相は、スズダルとニジニ・ノヴゴロドでの祝典について、「どちらかといえば無色透明」であると指摘した。熱気がなく、人出が少ない」のは、せいぜい「浅はかな好奇心」であろう。しかし、ヴォルガ川流域のコストロマで、初めて「熱狂に近いもの」が見られた。コストロマは、ロシアを最初に統治したロマノフ家のミハイルと深い関わりがあった。1613年、16歳の少年は、皇帝に選ばれたことを伝えに来た使節団から身を隠そうと、この街に近いイパティエフ修道院に避難した。300年後も同様に、ニコライとアレクサンドラを出迎えた群衆は熱狂的であった。そこにラスプーチンが現れ、すべてが変わった。
ラスプーチンはアレクサンドラの誘いでコストロマに来たのだろう、大聖堂で予定されていた盛大な礼拝の招待状を手にしたのである。彼は大胆にも、皇室が立つ場所から通路を挟んだ前方の目立つ場所に陣取ってしまったのだ。すると、会場のあちこちがざわめいた。人々は、このロシアで最も悪名高い男を一目見ようと張り切り、ささやき、指さされても、ラスプーチンは知らぬ顔で前方を見つめていた。警察長官スティーブン・ベレツキーは、ついにラスプーチンに目立たない場所に行くように言った。ラスプーチンは数歩動いただけで、注目の的であることに変わりはない。ラスプーチンは女性たちに微笑みかけ、意味ありげな視線を交わして、ようやく去っていった。
ラスプーチンは5月に皇室がモスクワに到着した際にも注目された。彼はクレムリンで、皇帝一行が城塞を通過するのを見守っていた。ニコライ2世の妹のクセニアは、「この農民がまたあちこちに出没している」と不満を漏らした。官憲や聖職者たちが抗議したが、無駄だった。「なんと不幸なことでしょう!」と、彼女は力なく締めくくった。
ラスプーチンの頻繁な登場は、民衆の支持を得ようとする政権の努力を損ない、彼が皇室の寵愛を受けているという事実を皆に思い知らせることになったからだ。ニコライとアレクサンドラは、自分たちが信じたいことを証明するために、いくつかの肯定的な瞬間をとらえた。皇后はある催しで、女官たちに「大臣たちがいかに臆病者であるか、これでおわかりいただけるでしょう」と言い放った。「彼らは常に革命の脅威で皇帝を脅しています。しかしここでは、あなた方自身がお分かりのように、私たちはただ姿を見せるだけで、すぐに揚げ足をとられているのです」。
ラスプーチンは、首都での最初の数年間は、経済的に不安定だった。彼は、より良い機会が訪れると、アパートからアパートへと移り住んだ。1913年、彼は友人の助けを借りて、イングリッシュ・プロスペクト3番地に「簡単なベッドと塗装された木のテーブル」のある一室を借りた。ラスプーチンはこの部屋を誇りに思っていた。そして、このアパートをニコラエフスキー通り70番地のもっと広いアパートと交換できたことを喜んでいた。
宮廷でのラスプーチンへの寵愛は、彼を金持ちにするものではなかった。アレクサンドラは彼に給料を払い、宮殿の礼拝堂で「聖なる像の前に昼も夜も灯るランプ」の手入れをさせているという噂が流れた。そんな職はなかったし、いずれにせよラスプーチンは賢すぎたので、皇帝夫妻に雇ってくれと頼むことはできなかった。ラスプーチンは神の仕事に忙しく、その時間は賃金で売るにはあまりにも貴重であると皇后は考えるのが最善であった。
実際、ラスプーチンはお金のことになると、皇后のことを “ケチだ、とてもせこい!” と文句ばかり言っていた。ラスプーチンにツァールスコエ・セローに来るように頼んだときでさえ、彼女は鉄道やタクシーの運賃を補償しないのが常であった。アレクサンドラはラスプーチンにポクロブスコエの自宅のための衣服や 聖像、小物などを贈った。しかし、彼女は首都での彼の生活の経済的なことは全く考えなかった。まれに皇后が現金を渡すことがあっても、それは嫌々ながらであり、彼がもっと欲しいと言えば、驚いているようだった。ラスプーチンは、宮殿への往復の交通費を友人からしばしば「借りた」。彼の出版社であり友人でもあったアレクシス・フィリッポフは、ラスプーチン自身が生きるのに必死であるにもかかわらず、「助けを求める知人に一日に何百、何千というルーブルをばらまく」という状況は皮肉で不条理だと考えていた。
アンナ・ヴィルボヴァも同様に、ラスプーチンがどこでどのようにお金を手に入れたのか見当もつかないと主張した。友人たちの慈善は役に立ったが、彼らは金持ちではなかった。彼の助けを求める農民はラスプーチンに鶏や 野菜、お菓子を与え、貧しい人々は魚や果物、パンを提供した。裕福な人々は、聖像やワイン、キャビアなどを携えてやってくる。アキリーナ・ラプチンスカヤはラスプーチンの財政を管理し、彼の影響力を求める人々からお金を集めた。彼女は初期の頃から信奉者で、やがてラスプーチンの秘書兼恋人となった。ラスプーチンは、彼女が金をくすねていると疑い、2度にわたって彼女を追い出した。そしてまた、彼女に戻るよう求めた。ラプチンスカヤは知的できちょうめんであり、ラスプーチンは彼の人生が着実に複雑化していく中で彼女を必要としていた。
ラスプーチンの経済状況は、1913年までに大幅に改善された。ラスプーチンは、役人に取り次いでほしい人たちから賄賂をもらうことを学んだ。ラスプーチンは1910年、コーカサスのかんがい事業のための国家融資を確保するために、ある実業家が彼に金を払ったとき、初めてその味をしめたのである。ラスプーチンの影響力が対価に見合うものであるという噂が広まると、他の「取引」も続いた。
ラスプーチンは今、暗黒面を歩いている。この段階が彼の神秘性を高めていた。新聞は “堕落した聖人ラスプーチン “や “ラスプーチン-時に汚い手も使うやり手 “という記事を掲載した。ラスプーチンはこれに対して無関心であると公言したが、彼はそれが気になった。「ジャーナリストはいつも私についてひどいことを書いている」と彼は不平を言った。彼は自分の新聞を作ろうと考えた。「民衆が必要としているのは、生きた言葉だ。そのためにお金を出してくれる人もいるし、宗教家も名乗りを上げてくれる。信心深い人たちを集めて、神がお望みなら鐘を鳴らそうと思っている」。しかし、ロシアでは新聞がほとんど売れていないことがわかり、この構想は立ち消えになった。
一方、批判する側にも揺るぎないものがあった。『イブニング・タイムズ』紙の社説は、ラスプーチンを名指しこそしなかったが、ある霊的な指導者が政治的な政策を指示したり、教会の人事に影響を及ぼしてはならないと訴えた。ロジャンコはその紙面をニコライ2世に見せると、困惑した様子でこう聞いた。「誰がそんな権力を握っているのだ?」。ロジャンコは「そのような者はロシアに一人しかいません。おわかりでしょう。彼は全ロシアの悲しみと絶望なのです」。
ツァールスコエ・セローの警備体制は、さらに人の興味を引き付けていた。1913年にヴォエイコフがこの任務を引き受けたとき、彼はラスプーチンの出入りを隠しもしなかったことを知り驚いた。ニコライ2世の日記によると、ラスプーチンは少なくとも月に一度は皇室に顔を出していたようである。しかし、ラスプーチンはオープンパスを持っていなかった。彼は、登場するたびに見張りが入場許可の電話をかけてくる間、待たされた。このことが噂話を誘発すると考えたヴォエイコフは、今後はこの農民をすぐに入門させるようにした。
ニコライは、ロジャンコや他の人がラスプーチンの議論に引き込もうとしても、ほとんど何も言えなかった。アレクシスはラスプーチンを必要としていたので、スパラの後の農民の地位は安泰であった。皇帝の日記によると、1913年7月16日、息子の「遊びで腕を振り回しすぎて右ひじが痛くなった。彼は長い間眠ることができず、とても痛がっていた、かわいそうに!」と記されている。ラスプーチンは翌日に到着した。「彼が出発するとすぐに アレクシスの腕の痛みは消え去った」「彼は穏やかになり 眠り始めた」皇帝が ラスプーチンについて何を言う必要があるというのだろう?
皮肉なことに、ラスプーチンに対する攻撃は、この時期のロシア社会を覆っていた神秘主義的なムードと相反するものだった。それ以前の忍び寄る宗教的シニシズムは、1913年には既存のキリスト教に対する完全な反抗として開花していた。知識人たちは退屈し、無名で猥雑で奇妙なものに気晴らしを求めた。ヴァシリー・ロザノフは、伝統的な道徳を嘲笑し、セックスこそが解放への道であると説いた。ゲオルギイ・グルジエフは、世界の偉大な宗教を統合し、「エソテリックキリスト教」あるいは「第四の道」と呼んで注目された。東洋の神秘的な教えは、おしゃれな社会で人気を博していた。災厄への恐れから快楽への熱狂をもたらしていた。ピーター・バドマエフとその神秘的なチベット産の薬草は、貴族たちが夕食の席で客にコカインを渡すようなサロンで、まったく違和感なく受け入れられていた。エソテリックな宗教は薬物中毒と新しいセクシュアリティと混ざり合っていた。
教会の指導者、貴族、プロレタリア、ロマノフ家の人々などで、同性愛は一般的になりつつあった。ウラジーミル・メシチェルスキーは、アレクサンドル宮殿の片隅で若い衛兵と姦通しているところを捕らえられたにもかかわらず、皇帝夫妻はメシチェルスキーを高く評価していた。皇后はメシチェルスキーを夫の「助け舟」「相談相手」と表現したこともある。
ラスプーチンはある意味で、首都を覆っていた新しいムードを反映していたのである。それでも、スパラでの彼の勝利の秋は、翌年には不満の冬に変わった。アレクシス・フィリッポフは、ラスプーチンが「落ち着いた精神的な静けさから、あらゆるもの、特に人生の意味に対する疑念と苦痛に満ちた幻滅の時期」に移行したことを指摘した。これは真の精神的危機であり、この地上での旅の終わりまで続いた。その原因がセックスとアルコールにあると考える人は、原因と結果を混同しているのかもしれない。ラスプーチンの友人たちは、1912年か1913年まで彼がほとんどアルコールに手を出さなかったと主張している。その後、彼らは「大きな変化」つまり危機を迎えたことを指摘した。ラスプーチンはアルコール依存症のように酒を飲んだ。彼の性欲も1913年から強くなり、より公然と表現されるようになった。
ラスプーチンは世俗的な成功によって、スピリチュアルライフが損なわれていた。彼は自分の霊的な才能が失われていくのを感じ、心が揺らいだ。彼は娘のマリアに、精神的な道を歩む初心者のように、もう一度やり直さなければならないと打ち明けた。しかし、それは装いに過ぎず、いかに自分が娘に認められたいかということの表れだった。彼の行動に変化があったわけではない。ラスプーチンは突然、アルコールなしで世界に立ち向かうことができなくなった。彼は定期的に大量に酒を飲み、生活は乱れたものになった。不眠症と悪夢に悩まされ、一人きりになる夜が一番つらかった。彼は、酒とセックスとジプシー音楽の世界に逃げ込んだ。
ラスプーチンが突然、催眠術の指導を必要としたのは偶然ではない。第10章で見たように、警察は1913年にラスプーチンに秘儀を教えることに同意したプロの男を除名した。しかし、彼はあきらめなかった。1914年2月1日付けの警察の報告書には、ラスプーチンが ジェラシム・パパンダート(ニックネームは”音楽家”)から催眠術を学んでいる、と記されているのだ。催眠術のレッスン:なんと皮肉なことだろう。人々はしばしばラスプーチンの治癒の才能を催眠術のおかげだと考えていた。しかし、ラスプーチンはその力を失うことを恐れたので、催眠術に頼ったのである。神の力が失われたのなら、人間の力が勝ったのだろうか?
ラスプーチンは信仰心や宗教的使命感を失うことはなかった。最後まで彼は教え、祈り、許しを請うた。しかし、1913年のラスプーチンは、10年前にサンクトペテルブルクに到着した時のような広い目を持つ放浪者ではなくなっていた。巡礼者は放蕩者になっていたのだ。大酒が彼の人生に与えたダメージを補うかのように、ラスプーチンは禁酒協会とその公的な活動(十字軍)を取り入れた。彼はウォッカを非難し、政府がウォッカの流通で利益を得てはいけないと主張した。ラスプーチンは禁酒を人々に呼びかけたが、自分はアルコールなしの生活を送ることが不可能であることを知った。1914年5月29日、新聞のインタビューに答えて、「ロシアに古くからある悪である酩酊と闘うことだ」と宣言した。「正当な理由がある」と続けた。「私たちに必要なのは、一般的な福祉に対する心や態度の変化であり、それが私たちが成功する唯一の方法なのだ」と。
ラスプーチンの生き方がサンクトペテルブルクを席巻する新しい意識と呼応していたとすれば、彼はバルカン半島での戦争の問題で世論と完全に対立していたことになる。19世紀を通じてトルコが衰退すると、ロシアとオーストリア・ハンガリーは半島の支配権をめぐって争うようになった。オーストリアはこの地域に関心を持ち、ロシアは同胞であるスラブ人を守ろうとした。1912年、セルビア、ギリシャ、ブルガリアがトルコを攻撃すると、サンクトペテルブルクの有力者たちは、ニコライ2世にスラブ民族の大義と彼らが共有する正教会を守るように求めた。1913年の春、ロマノフ王朝が300年を迎え、その栄光が揺らいでいるとき、戦争熱は特に高まった。
農民であったラスプーチンは、戦争がロシアに何をもたらすかについて、鋭い理解を持っていた。貴族は、軍隊を指揮し率い、高給と素晴らしい特権を得る機会を喜んでいた。一方、農民は、死と惨めさと愛国心の煽りを軍機から受けるだけである。ロシアの勝利さえも幻に終わるだろう。ラスプーチンはかつて、「我々はすでに世界最大の国だ。なぜこれ以上の土地が必要なんだ!」と言っていた。彼はまた、ドイツがロシアに勝つこと、そして同盟国がそれを防ぐことができないことも理解していた。敗北は革命と帝国体制の崩壊につながる。ラスプーチンが大切にしていた世界は、火と流血の奔流に押し流されることになり、何百万人が苦しみ、死んでいくだろう。
ラスプーチンは1913年の秋にサンクトペテルブルク公報のジャーナリストに対して、このような意見を述べたことがある。「戦争の恐怖と不和をなくし、敵意を助長してはならない。私たちロシア人は、争いを避け、平和のために働く人たちのために記念碑を建てるべきだ。戦争に反対する平和的な政策は、高尚で賢明なものと見なされるべきである」。彼はトルコを高く評価し、ロシアはバルカン半島のスラブ人を守るべきだという感傷的な考えを否定した。「私たちは “小さな兄弟 “の振る舞いを見てきた。今、我々はすべてを理解している」。
ラスプーチンは、ニュータイムズ紙のインタビュアーに対しても、同じように率直な意見を述べた。
”外国人にとって私たちのところに来るのはいいことだ。なぜなら、ロシア人はいい人たちで、魂は最高だ。最低のロシア人でも、外国人よりは良い魂を持っている。彼ら自身もそれを感じていて、魂を求めてやってくる。彼らには機械はあっても、それだけでは生き残れない。 彼らの周りはみんな良さそうに見えても、中身は何もない。 そして、それが重要なのだから。”
彼は、ロシア人はギリシャ人と共通の信仰を持っているのだから、ギリシャ人を支援すべきだという意見を否定した。アトス山には「多くの罪」があり、「修道士がすべき生活をしていない」と、元をたどれば皮肉な文句である。さらに、「キリスト教徒は戦争の準備をし、それを説き、皆をあおり立てる。戦争は悪いことだが、クリスチャンは服従するよりも、戦争に走る。キリストの教えを壊し、魂そのものを殺してしまうのだ」。
このインタビューでは、知恵くらべが行われた。ニュータイムズ紙の記者は、ラスプーチンの言葉をねじ曲げて不利な発言にしようと考えていた。ラスプーチンはヨーロッパの重要性を理解していない、バルカンのスラブ人を守るというロシアの名誉ある伝統を理解していない、等々である。しかし、ラスプーチンの演技は、彼の助言が最良のもので、いかに健全なものであるかを示していた。
結局、1913年の平和を維持したのは、フランスがロシアを支援しなかったからである。ラスプーチンの意見は、権力闘争のために後回しにされた。しかし、元首相セルゲイ・ヴィッテは、ラスプーチンの勇気ある行動に賛辞を送った。「バルカン戦争の時に決定的な言葉を発したのだから、彼は本物であると考えなければならない」。ロシア正教会と密接な関係にある新聞『ベル』は、「この最も無意味な流血からの救世主は、霊感のある『聖人』であり、ロシアを心から愛し、国の最高政治指揮に近く、誠実な預言者であると言われている」と指摘した。
ラスプーチンはこの危機を乗り越え、ほっとしたのも束の間、心配だった。彼は自分の勝利が間近に迫っていること、そしてそれが不安定であることを理解した。「私が生きている限り、戦争は許さない!」彼は宣言した。イタリアのジャーナリストがラスプーチンに、戦争は差し迫っていると思うか、と聞くと、「そうだ、戦争が起こると言っているし、彼らはそのための準備をしている」と答えた。「これは困ったことだ。戦争が起きないように、神がお守りくださいますように」。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』12
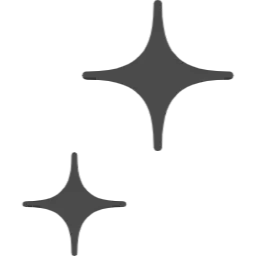
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

