『あなたは私たちのすべて』
1911年の夏、ラスプーチンには喜ぶべきことがあった。ピーター・ストリピンの任期は明らかに終わりに近づいていた。アレクサンドラは長い間この男を嫌っていたが、ニコライは彼の能力と忠誠心を高く評価していた。しかし、ストリピンは、ポーランド地方に関わる政治的危機をうまく処理できず、ニコライを避けていたところであった。ストリピンは、決して一緒に仕事をするのが楽な人物ではなかった。ニコライは、ついにストリピンを辞めさせる時が来たと判断した。夏には、ストリピンがコーカサス総督に就任するという噂が首都を駆け巡った。それは、かなりの降格であった。
ストリピンは、首相と警察を統括する内務大臣を兼任していた。この2つの職を兼ねることで、ニコライは、1905年の革命鎮圧を任務として、ロシア国家の全権を一人の人間に握らせることになった。皮肉なことに、ストリピンはこれを成功させたため、もはや欠くことのできない存在となった。多くの国家元首がそうであるように、ニコライも自国の官僚をあまり信用していなかった。ストリピンの後継者を探すために、保守派のジャーナリスト、ゲオルギー・サゾノフに依頼をした。また、ラスプーチンの助言も仰いだ。ニコライは運命的な決断をした。初めてラスプーチンを最高レベルの国政に関与させることになったのだ。
ニコライ2世は、セルゲイ・ヴィッテかウラジーミル・ココフツォフを首相にと考えていた。ヴィッテは1905年に首相に就任しており、ニコライは個人的に彼を嫌っていたが、広く賞賛されていた。ココフツォフは才能がないとはいえ有能で、財務大臣として万人の賞賛を集めていた。ニコライは、内務大臣としてアレクシス・フボストフに関心を寄せていた。フボストフは39歳で、実力と努力、そして上に取り入る才能で地方官僚の中で出世していた。1911年、フボストフが皇帝の目に留まることになったのは、実に大胆な行動からだった。ストリピンが退陣するという噂を聞いた彼は、自分が内務大臣になった場合の政策をまとめたメモを提出した。ニコライは感心したが、この青年には負債があることも知っていた。
フボストフは、「憎たらしいほど太っている」と言われ、一般には悪党とされていた。しかし、「明るい青年、精力的で進取の気性に富む、ただし国事には向かない」と評されたこともある。叔父のアレクサンドル・フボストフ(後に司法大臣に就任)は、皇帝に「私の甥は策略に長けているが、国家公務とは無関係なことに専念することになるだろう」と述べ、一般的な意見を代弁している。「彼は聡明だが、自分の動機や考えを批判することができない、不向きな人物だ」。フボストフに関する噂は、かなり否定的なものだったが、それでも彼は皇帝を魅了した。ニコライは、この青年の中に、他の人が見落としている何かを探っているようだった。
ニコライ2世はサゾノフとラスプーチンに、彼が総督を務めていたニジニイ・ノヴゴロドにフボストフを訪ねるよう依頼した。ラスプーチンが「彼の魂を見つめる」間、サゾノフは政治的な問題を議論することになった。フボストフはラスプーチンが誰であるか、なぜ彼が重要であるかという観念がなかった。「私はラスプーチンと冗談話をした」と彼は後に認めた 「しばらくして私は警察官を呼んで彼を駅まで送った」。
この後すぐに、ラスプーチンは農奴制廃止50周年の盛大な祝典のためにキエフに向かった。ストリピンは皇帝に同行していたが、これが二人の最後の仕事となった。ラスプーチンは歩道に立ち、これらの高官を称えて行われたパレードを眺めていた。彼は突然、これから悲劇が起こり、それに続いて恐ろしいポグロムが起こることを予感した。ラスプーチンは、ストリピンの馬車が通りかかると、非常に興奮した。”死が彼を追っている!” ラスプーチンは叫んだ。「死が彼の背中に乗っている!ストリピンの背に!”信じないのか?」ラスプーチンはその夜、寝返りを打ちながら何度もつぶやいた 「死が来るぞ! “信じないのか?」実際、誰も彼の話を真剣に聞いていなかった。
翌日1911年9月1日の夜、リムスキー・コルサコフの「ツァーリ・サルタン物語」の祝祭公演があった。ニコライ2世は娘のオリガとタチアナと一緒に貴賓席に座り、ストリピンは1階席の前方に座っていた。休憩時間に学生がストリピンを撃った。医師は彼の回復を見込み、ニコライは予定されていたウクライナ視察に出発した。5日後、ストリピンが死ぬと、皇帝は病院に駆けつけ、倒れた彼の枕元にひざまずいて、「許してくれ」と何度もささやいた。
ニコライとその家族はストリピンの葬儀に参列しなかったが、これを偉大な政治家に対する敵意の表れだと考える人もいた。真実はもっと複雑で、最近になって明らかになった証拠によれば、アレクサンドラは同時代の人々や歴史家たちから不当に評価されていたことがわかる。ラスプーチンの熱烈な敵であったことからストリピンを嫌っていたが、彼の命が奪われたことに動揺していた。 1911年9月2日付の義姉エレオノーレへの手紙の中で、アレクサンドラはストリピンが回復するという一般的な意見と同じことを言っている。彼女は、ストリピンが「5時間眠り、大きな痛みもなく」、意識を失うこともなく、「非常に明晰に」話していることに感謝した。 アレクサンドラはこう続けた。「危機は脱したようで、肝臓が少し悪くなっただけらしい…。タチアナは泣きながら帰ってきて、まだ少し震えているが、オルガはずっと勇敢な顔をしていた… 神よ、彼が完全に回復することを祈っています。私はそこに一緒にいなかったけど、とてもひどい悲しい出来事です」。
アレクサンドラは、ストリピンが息を引き取ったという知らせに「神経的なショック」を受けているのを目撃されている。彼女は後に、”我らが友を奪い、神を怒らせた者は、もはや神の保護を期待することはできない “という意見を表明した。ラスプーチンは、ストリピンが危険な状態にあることを知らせ、ストリピンが生死をさまよっている間、皇后を慰めるためにできる限りのことをしたというのが、彼の功績であった。5年後、ニコライがキエフを訪れた際、「我々の古い部屋を見て回ると、過ぎ去った日々と哀れなストリピンの死が思い出された」と感想を述べている。
ニコライは、ストリピンの後継にウラジーミル・ココフツォフを政府のトップに抜擢した。新首相は、アレクシス・フボストフを内務大臣に任命することに反対していた。ストリピンが暗殺され、ロシアが危機に瀕している今、フボストフに内相として必要な「一つの資質」があるとは思えなかったのだ。ニコライは、ココフツォフの希望する堅実で経験豊富な官僚、アレクサンダー・マカロフを尊重した。
この危機は、ある意味でユーモラスな形で幕を閉じた。ラスプーチンを疎外したのは間違いだったと知ったフボストフは、急いでサンクトペテルブルクに謝りに行った。しかし、ラスプーチンは頑として首を縦に振らない。彼はフボストフに、すでにアンナ・ヴィルボヴァに電報を打ち、「神は彼とともにあるが、彼には何かが欠けているとママに伝えてくれ」と頼んだという。フボストフはニコライの興味をそそり続け、皇帝は死の炎に吸い寄せられるようにフボストフに引き寄せられた。フボストフは4年後の1915年、内務大臣に就任した。
ラスプーチンは「私は永久に去るつもりであり、意見を交換するためにあなたに会いたい」とフボストフに手紙を書いていた。「いついがいい?」。ラスプーチンは首相官邸に入ると、何も言わずに座った。「彼の目は私をじっと見ていた」とココフツォフは回想している。「彼の目は眼窩に深く入り、寄り目で、小さくて、色は鋼鉄の灰色だった。まるで催眠術でもかけているようだった。それとも単に私を探っていたのだろうか?」
ラスプーチンはついに聞いた。「それで、私は去るべきかな?私にはもう生きる道がない、みんな私のことを噂している!」
「そうですね、お帰りになったほうがよろしいかと思います」フボストフは答えた。「あなたの居場所はここではないし、あなたは宮殿に現れて、最も突飛な観念や結果を与えて、君主を脅かしているのです」。
“わかった、私が悪いんだ” ラスプーチンはつぶやいた。「私は出て行く。何か私に用があったら、私はかかわらないと言ってくれ」。ラスプーチンはしばらく首相を見つめていた。まるで首相が何か和らげるようなことを言う機会を与えるかのように。ラスプーチンはついに椅子から飛び降り、「さようなら!」と言いながら去っていった。
この面会は試練であった。 ココヴツォフは政府のラスプーチンに対する撃退を続けるのか、それともほどほどに対応するのか、アレクサンドラはそれを知りたがった。新首相は、ラスプーチンを問題視し、追放を考えたことがうかがえる。ラスプーチンはアレクサンドラに、ココヴツォフが自分をサンクト・ペテルブルクから追放すると脅したことを話したらしい。数日後、ニコライはその件について尋問した。ニコライは、彼がそのようなことは言っていないと否定し、「我々のせいで誰かが不快な思いをするのは残念なことだ」と言った。続いて皇帝は、ラスプーチンについての意見を求めたが、これも試練だった。ココヴツォフは皇帝に、ラスプーチンは「典型的なシベリアの浮浪者」であり、彼が中央監獄局で出会った囚人たちと同じであると言った。「あのような人たちは、唇に微笑みを浮かべながら十字架のサインをする一方で、あなたの喉をつかんで絞め殺すのです」。
1912年、ラスプーチンをめぐる新たな危機が勃発した。マイケル・ノヴォセロフは1910年に『グレゴリー・ラスプーチンと神秘的堕落』と題する小冊子を出版し、ラスプーチンに関する古い話題を再利用し、一部は真実、一部は虚偽であると主張した。ノボセロフは、シベリアの神秘主義者でヒーラーであるラスプーチンはクリストであったが、「高い地位」の人々によって支持されていると主張した。そのことを裏付けるかのように、警察は出版社を襲撃してパンフレットを押収し、版木を破壊した。ラスプーチンを守っていたのは、本当にある種の権力者だったのだ。
アレクサンドル・グチコフは、この事態を嘆いた。彼はオクトブリスト党の指導者であり、第三国会の議長であり、抜け目のない戦術家であった。保守派の彼は、かつて皇帝と協力してロシアに立憲君主制を築きたいと考えていた。しかし、ニコライの考えは違っていた。彼は、自分は依然として独裁的な支配者であると考えていた。ニコライは、国会の設立は間違いであったと考えていた。ニコライは、グチコフやオクトブリストの意見を聞くのが得策であったかもしれない。しかし、皇帝に拒絶されたときのグチコフの反応は、問題になるかもしれなかった。
グチコフの同盟者たちも、彼が「落ち着きがなく人に敵意を抱かせる野心家」であることを認めている。ラスプーチンは、ニコライとアレクサンドラが愚鈍で、ロシアにおける立憲政治の発展を妨げているというグチコフの主張に対して、常に新しい証拠を提供し続けていた。グチコフは第三国会議長として、スタレッツに関する討論会を計画した。また、ロシアの主要な日刊紙「モスクワの声」の支持も得ていた。検閲官はジャーナリストにラスプーチンの活動について論じる権利を与えたが、彼とロマノフ家の一員を名指しで結びつけることはできなかった。しかし、「編集者への手紙」なら許されるので、グチコフはノヴォセロフの小冊子をそのまま掲載した。それを読んだとすれば、数千人がラスプーチンを「人々の魂を堕落させ、教会を隠れ蓑にした不謹慎な謀略者」として非難するのを目にすることになったのだ。
他の新聞社もノヴォセロフ氏の記事を取り上げ、話を膨らませた。警察は当局の機嫌を損ねた記事を掲載した新聞を押収し、また、売れ残った新聞は莫大な金額で売られた。ラスプーチンは、他の誰にもできないことをやってのけたのである。彼はニコライの批判者たちを、「悪名高いスタレッツと政府との関係を暴露する」という共通の目的のもとにまとめていた。
1912年に開催された第四国会では、新大統領が選出された。代議員たちは、同じくオクトブリストの指導者であるミハエル・ロジアンコを選んだ。彼は前任者とは全く違っていた。グチコフがニコライ2世の権威を失墜させようとしたのに対し、ロジャンコは皇帝を愛し、ラスプーチンを復帰させることによって、政府の信頼を回復するようニコライを説得する使命を帯びていた。
ニコライは、証拠を誠実に調査すれば、心の広い人なら誰でも、ラスプーチンは彼に対してしばしば指摘されるような罪には問われないと分かるだろうと考えた。彼はロジャンコに状況を調査し、その結果を報告するよう依頼した。ロジャンコは喜んだ。彼はまた、ラスプーチンに関するすべてのファイルや文書を見直すことを決意した。しかし、そのような野心は明らかにニコライが考えていたものとは違っていた。
シノドからラスプーチンに関する資料を入手するのは困難だったが、ロジャンコは何とかそれを手に入れた。翌日、ラスプーチンの盟友でオベリスク補佐官のピーター・ダマンスキーがロジャンコの事務所に現れ、資料の返却を要求した。ダマンスキーはよく相手をいじめて服従させるが、体格のいい大統領を脅すことはできない。(ロジャンコが「ロシアで一番太っている男」と自己紹介したら、ツァレヴィチのアレクシスに大笑いされたことがある)。ダマンスキーはようやく、書類を取りに行かせたのは皇后であることを認めた。
ロジャンコは、アレクサンドラにも他のロシア人と同じように皇帝の命令に従う義務があると主張した。そしてダマンスキーに、「彼女の希望には添えない」と伝えるよう命じた。ロジャンコはとても鈍感だった。ココフツォフら高官たちはニコライの目的をすぐに理解したが、ロシア一の太っちょは全く理解できなかった。皇帝はロジャンコがラスプーチンをお馴染みの罪状で無罪にすると思っていた。しかし、国会の議長は、それらが真実であると結論づけた。このため、1912年2月26日、ニコライとの会談は非常に緊迫したものになった。
ロジャンコはまずラスプーチンを批判し、皇帝の機嫌を損ねたら黙ると申し出たが、王位への忠誠には正直さが要求される。ニコライは黙って頭を下げ、タバコを一本ずつ吸いながら、彼の発言を許した。ロジャンコが、ラスプーチンが司祭の格好をしている写真を見せると、苛立った皇帝は「そうだ、これは行き過ぎだ」と答えた。「彼に胸章をつける資格はない」と。しかし、ラスプーチンを首都から追放する要請を、ニコライは却下した。
このスキャンダルは、アレクサンドル宮殿にも影響を及ぼし始めた。廷臣たち、つまり朝廷に仕える男女はラスプーチンを軽蔑し、ついにラスプーチンに対抗する立場をとることを決意した。彼らは皇帝とその妻に話をするために協調して(秘密裏に)反対運動を開始した。もちろん、彼らの努力は失敗に終わった。ニコライは一人一人の話を丁寧に聞き、最後に「この話はもうしないでくれ」と締めくくった。一方、アレクサンドラは激怒した。「聖人はいつも中傷されている」と、主治医のボトキン医師に訴えた。皇后は、ラスプーチンへの非難が事実であることも知っていたが、このスキャンダルはすべて嫉妬からきていると主張した。「私たちが彼を愛しているから、彼は嫌われているのよ」とアンナ・ヴィルボヴァに言った。
ニコライは嵐が過ぎ去ることを期待したが、実際には新たな危機が訪れていた。神聖シノドの予算が国会で審議されることになり、ラスプーチンの敵はこの機会を利用して彼を攻撃したのだ。グチコフがウラジーミル・サブラーに、農民に教会の政策に口を出させるのはおかしいと攻撃すると、拍手が沸き起こった。グチコフは、誰かが自分を弁護してくれるのではと、緊張した面持ちで周囲を見回した。エブロギイ司教が演説に立った。彼は大きな名声を持っていた。彼は選挙で選ばれた副議長であり、シノドの統治評議会に席を置いていた。彼はサブラーが高潔な人物であることを知っていた。残念ながら、彼は皇帝に立ち向かおうとしない弱虫でもあったし、ラスプーチンが教会の問題に干渉することを許していた。
エブロギイは、「検察官が自分の名誉を守ってくれることを期待する」とつぶやいた。サブラーはそれを見事に実行した。しかし、その攻撃が正当化されることは誰もが知っていた。サブラーの指導の下、”教会は評判を落とした”、”ラスプーチンは教会を泥沼に投げ込み教会に関係するもの全てに悪意を与えた”。
ラスプーチンが国会の議論の対象になったのはこれが初めてだった。代議士たちは有権者から苦情を受けていた。ある者はラスプーチンの悪行を直接知っていると述べ、別の者は彼がクリストであると主張した。また、単に情報を求める者もいた。リベラルなカデット党のリーダーであるポール・ミリュコーフは、1910年にラスプーチンに会ったことのあるという男性から話を聞いた。彼は、ラスプーチンが「人々に精神的な安らぎを与えた。困難な問題や病気について彼らを助けた。彼は助言を与え、霊的な生き方に献身する者、聖なる者と自己紹介した “と述べた。しかし、ミリュコーフの代理人は、”本当のラスプーチンは何者なのか?異端者なのか、それとも正義の味方なのか?”と疑問を呈した。
それは実際、素晴らしい問いだった。ラスプーチンはニコライとアレクサンドラとの関係を常に自慢していた。壁に飾られた皇帝の肖像画、家中に吊るされたランプ、皇后が彼のために刺繍したシルクのシャツなどを人々に見せていたのだ。このような傲慢な態度が裏目に出るのは時間の問題であった。第7章で見たように、1909年、イリオドールがポクロブスコエでラスプーチンとクリスマスを過ごしたとき、それは起こったのである。ラスプーチンは、皇后とその子供たちからの手紙の束を客に見せた。イリオドールは、ラスプーチンが7通の手紙をくれたと主張した。それとも、イリオドールが盗んだのだろうか?
イリオドールは明らかにラスプーチンの敵に手紙を渡した。1911年後半にサンクトペテルブルクで、それが印刷され現れ始めたからである。誰がそれを公開したのか。ニコライはグチコフを疑い、ココフツォフやミリュコーフも疑ったが、誰が出版したのかはまだわかっていない。
今日、これらの手紙はスキャンダル雑誌の裏ページを飾ることはないだろうが、ラスプーチンが皇室の生活にいかに深く入り込んでいたかを示している。長女のオルガは、ある若い将校に想いを寄せていることを告白し、ラスプーチンは「あまり彼に会わないように」と忠告している。また、アレクサンドラの健康状態が悪化していることもうかがわせる。オルガは、「神様、ママがこの冬はもう病気になりませんように」と書き、母親との不安な関係にも言及している。オルガは、アレクサンドラが「ひどく憂鬱で気難しい人でなくなるように」と願っていた。タチアナは次女で最も従順な娘であり、アレクサンドラに最も気質が似ていた。彼女はラスプーチンに「私があなたに対して犯したすべての罪を許してください」、「私たち罪人を許すよう神にお願いしてください」と頼んだ。三女のマリアはラスプーチンから贈られた聖書を持って眠った。彼女は母が「神様のことで二人きりで会うことを許してくれる」ことを願ってた。”一緒に神に祈ることができたら素晴らしいことです”、と言った。ラスプーチンが少女たちと不適切な関係を持っていたという考え方に反論していることに、皮肉屋はおそらく気づかなかったのだろう。
最もダメージが大きかったのは、1909年2月7日付のアレクサンドラからの手紙だ。
『愛するあなたが、一緒にここにいてくれたことは、言葉にできないほどの喜びです。どう感謝したらいいのでしょうか? 私の願いはただ一つ あなたの肩で眠りにつくことです。 あなたは私たちのすべてです。私の先生、私を許してください。多くの罪を犯しました。まだ今も犯しているのです。 許し、耐えてください。私は良いクリスチャンになりたい、良い人間になりたいと願っていますが、それはとても難しいことです。私を救ってください。見捨てないでください。私は弱く、善良ではありません。あなたを愛し、信じています。神様、私たちがすぐに会える喜びを与えてください。あなたにキスを。祝福と許しを。』
ココフツォフとニコライは、ようやく回収された文書が本物であることを確認した。数ヶ月の間に流れた噂から、人々はアレクサンドラの手紙が彼女とラスプーチンが恋人同士であることを証明したように感じた。しかし、これは不朽のでっち上げ話であり、事実ではなかった。当時は誰も、手紙がラスプーチンの手から抜け落ちて出現していることに気づいていなかった。しかし、この手紙はラスプーチンの手から離れていたのである。そして、それは予期しない新しい問題を引き起こした。「マカロフと私は、この手紙をどうしたらいいのか分からなかった」とココフツォフは振り返る。「しかし、内務大臣がニコライに渡すと、皇帝は青ざめた。「彼は緊張して封筒から手紙を取り出した」。ニコライはアレクサンドラからの手紙を見て、「そうだ、これは偽の手紙ではない」と唸りながら、その包みを机の引き出しに放り込んだ。「これでお前の免職は確実だ」と、ココフツォフに警告した。そして、その予言は数週間後に的中した。
アレクサンドラはポクロブスコエに怒りの電報を打ち、ラスプーチンの不注意を叱責した。ラスプーチンの言い訳は、イリオドールが手紙を盗んだに違いないというものだった。しかし、皇后は弁解する気にはなれず、ラスプーチンが急いで都に戻っても拒否した。アンナ・ヴィルボーヴァは、かつて皇帝のお気に入りだった男が、復活祭のためにクリミアへ旅行する際、一家に加わってくれることを望んでいた。これが許しと和解の時であることを知っていたのだ。しかし、ニコライはこれを拒否した。ヴィルボヴァがラスプーチンを汽車に乗せたと知ると、彼とその荷物は次の駅に捨てられた。
それでもラスプーチンはヤルタに向かい、その到着に舌を巻いた。廷臣のウラジーミル・オルロフ王子は「これで安心だ」と皮肉った。「ラスプーチンが来たからには、すべてがうまくいくだろう!」と皮肉った。
実際、ラスプーチンにとって物事は「うまく」いかなかった。何年もの間、人々はニコライとアレクサンドラにラスプーチンとの友情を終わらせるよう説得していたが、成功しなかった。どうやらどんな噂やスキャンダルも彼らを引き離すことはできなかったようだ。ラスプーチンのキャリアが突然終わりを告げたとすれば、それは彼自身の判断の甘さのせいである。しかしラスプーチンは、神がロマノフ家を救うために自分を送ったのだと、まだ確信していた。彼は自分の使命を取り戻すことを願いながら、待つことを余儀なくされた。そして、1912年10月2日、事件はまったく違う方向へ動き出した。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』10
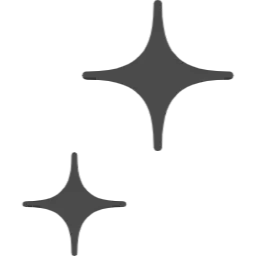
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

