『神はあなたの祈りを聞いてくださった!』
皇帝一家は半世紀にわたり、宮廷生活の圧力や監視の目を逃れてポーランドで狩りを楽しんでいた。1912年9月、一家はブレスト・リトフスク近郊の広大なビャロウィエザに到着し、ニコライが自然と触れ合い、家族がくつろぐことができるようになった。8歳になった皇子アレクシスは、ある日、ボートに飛び込もうとして転倒。左下腹部に内出血を起こし、アレクシスは寝込んだ。熱は上がり、数日、アレクシスは再び危機に直面するかと思われた。しかし、腫れは不思議と治まり、9月16日にはすっかり良くなったので、ロマノフ家はスパラの狩猟保護区に移動することになった。
スパラのロッジは、森の端にある荒れ果てた木造家屋で、部屋はとても暗く陰気で、明るい日でも電気をつけっぱなしにしなければならないほどだった。ニコライは狩りをし、大公女はテニスをし、アレキサンドラは日光浴を楽しんだ。森でピクニックをしたり、ポーランドから来た貴族をもてなしたり。ただ、アレクシスの健康状態だけが、この田園生活の世界を乱していた。アンナ・ヴィルボヴァは、この時の彼を「顔色が悪く、明らかに調子が悪い」と表現している。実は、ビャロウィエザで転倒した傷がまだ癒えておらず、家にいなければならずに落ち着いていられなかったのだ。ある日、アレクサンドラは彼をドライブに連れ出した。馬車は凸凹道を揺れ動き、アレクシスはすぐに痛みを訴えた。帰りは悲鳴を上げ、スパラに着く頃にはほとんど意識を失っていた。1912年10月2日、悪夢の始まりである。
ユージン・ボトキン医師は、左大腿部上部の鼠径部付近にひどい出血を発見した。少年の体温が急激に上昇したため、紫色の腫れができていた。内圧が非常に高かったので、皇子は医師に腫れを診察させなかった。サンクト・ペテルブルグから夜行列車で来たセルゲイ・フェドロフ医師が到着した時には、出血はさらにひどくなっていた。股間から腹部にかけて血がにじんでくるので、アレクシスは痛みを和らげるために左足を上げたが、内出血がますます強く神経を圧迫して、その体勢は耐え難いものであった。皇子は錯乱し、意識が遠のいていく。悲鳴と絶望的なうめき声が交互にロッジに響いてくる。主よ、憐れみたまえ……」と言いながら。
「ママ、助けて!」と泣き叫ぶ息子を、アレクサンドラは何時間もベッドサイドにいながら、どうすることもできなかった。ニコライは妻を休ませたが、「私よりも妻の方が試練に耐えている」と認めている。しかし、息子の苦しみに圧倒され、泣きながら寝室から逃げ出したこともあった。その秋、アレクサンドラの妹であるプロイセン王女イレーネがスパラに滞在していた。皇帝は彼女を「私たち二人にとっての天の恵み」と書き記している。イレーネは、ニコライが「とても心優しく、冷静で、どんな状況でも落ち着いている」と書いている。
1904年に一人の子供を血友病で失ったイレーネは、もう一人の血友病の息子であるワルデマールを常に心配していたのだ。1904年に一人の子供を亡くした彼女は、もう一人の血友病の息子、ワルデマールをいつも心配していたのだ。アレクサンドラもアレクシスも、彼のか弱い命が少しずつ失われていくことに気づいていた。彼は時折「僕が死んだら、もう痛みはないんでしょうね?」と母親によく聞いていた。自分が死んだら、「森の中に石の小さな記念碑を建てて」と両親に頼んだ。
使用人や家人たちは、耳に綿を詰めて仕事をした。アレクシスが血友病であることは極秘にされていたので、彼がなぜ苦しんでいるかは推測するしかなかった。ロシアの王位継承者が瀕死の状態でありながら、皆が普通に生活しているという異常な状況であった。ニコライは狩りをし、大公夫妻はテニスをし、アレクサンドラはポーランド貴族のためにお茶や晩餐会を開いていた。それは、アレクシスの病気の秘密を守るための、平凡さを装った行動だった。
宮廷生活10年目、子供たちのフランス人家庭教師ピエール・ジリアールは、偶然にも一家の恐ろしい秘密を知ってしまった。ある晩、地元の貴族たちが、マリアとアナスタシアがモリエールの『ブルジョワの紳士』の一場面を演じるのを楽しみにやってきた。両親は正面に座って客と談笑し、ジリアールはそれを横目で見ていた。皇后がゆっくりと席を立ち、席を外すとすぐに息子の枕元に駆け寄り、「気が動転して恐怖におののいた顔」をしているのを彼は見た。彼女はすぐに社交に戻り、微笑みながら、彼女の人生を支配していた悲劇的なゲームを続けていた。
10月6日、アレクシスの熱は急激に上がった。血尿と腹膜炎が始まったのだろう。その夜、フェドロフは両親に、息子の胃から出血していることを告げた。ニコライはようやく、皇子が病気であることを世間に知らせるために、定期的に医療報告書を発行することに同意した。しかし、血友病のことは一切触れず、今もごまかしが続いている。カザンの聖母マリア大聖堂には、大勢の人々が集まり、ロウソクを灯し、少年の回復を祈った。少なくともスパラでは、平穏な日常を装うことができなくなった。敷地内には教会がないので、芝生の上にテントが張られた。皇子たちの宗教指導者であるアレクサンドル・ヴァシリエフ神父が祈りを奉げた。「使用人、コサック、兵士、その他すべての人々がとても同情的だった」と、ニコライは後に母に書き送っている。「ポーランドの農民は大勢でやって来て、涙を流していた」。
その後2日間、何百万人もの人々が祈りを捧げたが、アレクシスは悪化していった。10月8日、ニコライが来賓と昼食をとっていると、アレクサンドラから急ぎ足で書かれたメモが届き、終わりが近いことを警告してきた。ニコライは息子のベッドサイドに駆けつけ、疲れ果てた妻とともに、なすすべもなく見守った。ヴァシリエフ神父が最後の儀式を行い、翌日には皇子の死を伝える医学公報がすでに出来上がっていた。状況は悲惨だったが、アレクサンドラはまだ希望を捨てていなかった:まだラスプーチンがいたのだ。
ラスプーチンへの懇願は最後の必死の行動であり、明らかに苦闘の末のものであった。ニコライとアレクサンドラのラスプーチンへの信頼は薄れていたが、状況的に選択の余地はなかった。ラスプーチンは何千キロも離れていたが、アレクサンドラは彼の祈りを求め、アンナに自分の代わりにポクロブスコエに電報を打ってくれるよう頼んだ。
その答えは、翌朝早く届いた。アレクサンドラが居間に現れたとき、疲れ切って怯えていた母の姿ではなく、笑顔で穏やかな表情をしていた。アレクサンドラは、「お医者様からはまだ改善が見られないと言われていますが、私自身は少しも不安はありません。夜にはグレゴリー神父から電報が届き、すっかり安心しました」と告げた。その電報は短く、直接的であった。”小さき者は死なない。医者が彼をあまりかまわないように “。
ラスプーチンは実際には2通の電報を送ったと、アレクサンダー・スピリドビッチは書いている。1通目は「恐れることはない、病気は彼らが言うほど危険ではない。医者が彼をあまりかまわないように “とあった。スピリドビッチは2番目の電報を引用していないが、それは神が彼女の祈りを聞き、それに答えてくれたことをアレクサンドラに断言するものであったとされている。神話作りは、その場のドラマと詩情を盛り上げることにこだわっていた。ラスプーチンの一通の電報には、「神はあなたの涙をご覧になり、祈りを聞いてくださった。悲しむなかれ。小さき者は死なない。医者が彼をあまりかまわないように”。これは、イザヤ書38章5節、ヒゼキヤ王が「わたしはあなたの祈りを聞き、あなたの涙を見た、あなたの命を15年延ばそう」と言われたことと類似している。また、スピリドビッチの2つの電報を1つのテキストに混同している。
この後の展開は、どうやら不可解だった。1912年10月9日の午後2時に、アレクシスが穏やかになったことをニコライが日記に記している。彼は、熱も下がり眠った。その後24時間の経過は、医師たちが危機を脱したという報告を出すほど、目覚しいものであった。2日後には出血も止まり、腫れもひいてきた。スパラでのテントの教会では、回復を祈る声から感謝の声に変わった。ニコライは狩りに戻り、アレクサンドラは客人たちと夕食を共にすることが多くなった。
「アレクシスの回復は非常に時間がかかるだろう」とニコライは母親に書いている。彼は「まだ左ひざに痛みがある。枕に支えていなければならない。しかし、医師たちはそんなことは気にもしていない。一時は手足も顔も、まるで蝋人形のような顔をしていたが、今はすっかり良くなった。手足、顔、すべてだ。ひどく痩せてしまったが、医者たちは精一杯詰め込んでいる。左足がまっすぐになるまでには、何ヵ月もかかる。それでも、面倒な鉄の装具をつけ、泥風呂に入り、マッサージをして、萎縮した筋肉をよみがえらせなければならない。しかし、彼は生きている」。
スパラで何が起こったのか、正確に解明することは不可能である。日付も詳細も不明のままである。アンナ・ヴィルボヴァはいつラスプーチンに電報を打ったのだろうか?彼の返事は早朝にスパラに届いたのか、それとも皇子が既に回復し始めた後だったのか?ラスプーチンはアンナが記述した1本の電報を送ったのか、それともスピリドビッチが言及した2本の短い電報を送ったのか?
アレクシスの回復は最大の謎だった。致命的な発作ではないので、危機は頂点に達し、自ずと治癒が始まったと思われる。しかし、医師たちはある時期から希望を失っていた。フェドロフは、「奇跡でしかない」と言い、その確率は100分の1以下だと考えていた。その時、医師たちは不確かだった。
それとも、そうなのか?フェドロフは当初、圧迫を和らげるための手術を拒否していた。しかし、状況が悪化するにつれ、宮廷長官モソロフに、「もっと抜本的な対策が緊急に必要だが、それにはリスクが伴う」と言い出した。「しかし、それにはリスクが伴う。どうだろう。それとも、皇后に知らせずに処方した方がいいのだろうか」。モソロフは、フェドロフが考えていたかもしれない「抜本的な対策」を説明しなかった。おそらく内出血を止めるための手術だったのだろう。後日、アレクシスが回復したとき、モソロフは外科医に、自分が考えていたような手段に出たかどうか尋ねた。「もし、そうだとしたら、認めないわけにはいかないだろう。この辺の事情はおわかりでしょう」と答えた。これは否定したことにはならない。フェドロフは、皇子の回復が「医学的にみて全く不可解」であることを後に認めている。
スパラは、ラスプーチンが幼い患者の血友病にどう対処したかという、より大きな問題につながっている。ラスプーチンはアレクシスを「治した」「癒した」とよく言われるが、それは明らかに言葉の綾である。アレクシスは生まれたときから死ぬまで血友病だったのだ。ラスプーチンが歴史に名を残すことになったのは、それぞれの発作の症状を軽減させることができたからである。彼の成功の秘密は何だったのか?ラスプーチンはアレクシスに薬を投与したのか?彼は催眠術を使ったのか?自己暗示だったのか?今の私たちには思いもよらないような奇妙な能力を持っていたのだろうか?
血友病は、当時の専門医師たちを困惑させ、その発作の痛みを和らげることさえできなかった。1885年に出版された一般向けの権威ある資料には、この病気にかかった男性は「傷の有無にかかわらず顕著に出血しやすい性質がある」と記されている。ある時は、ぶつけたり、打撲したりしても何事もなく過ぎるかもしれないが、別の時には「信じられないほど痛い」危機をもたらすかもしれないのである。鼻、口、喉からの自然出血はよくあることで、避けられないものであった。このような場合、医師は全く無力であった。
しかし、ラスプーチンは大成功を収めた。ある宮廷関係者は、「私が疑う余地のない正直な人々」から、アレクシスの医師は「出血を止めることができなかった」しかしラスプーチンが現れて、祈ると出血は止まったと聞いたと報告している。モソロフは「ラスプーチンは治癒の腕において疑う余地のない成功を収めた」と認めている。「どうやったのか見当もつかない」 宮廷の医師たちはラスプーチンを軽蔑していたが、苦痛を和らげる彼の能力をしぶしぶ認めていた。 「アレクシスが出血したとき、私はどんな方法でもそれを止めることができなかった」とフェドロフは証言した。しかしラスプーチンは「何気なく病人に近づき、ほんの少しの時間で出血が止まった」と証言した。オストロゴルスキー博士はラスプーチンを嫌っていたが この高名な小児科専門医はラスプーチンが何度か「世継ぎに救いを与えるのを個人的に見た」と認めている。
ラスプーチンの敵の中には、ラスプーチンが「宮廷の侍女、おそらくアンナ・ヴィルボヴァの助けを借りてアレクシスにこっそり薬を飲ませた」と思い込んでいる者もいた。ラスプーチンが現れる直前に薬は止め、皇子は回復し、アレクサンドラは「これをラスプーチンの癒しの力のおかげだとした」という。もう一人、ラスプーチンの共犯者として疑われたのが、東シベリアのブリヤート族に属するピーター・バドマエフである。バドマエフは、戦争前夜のサンクト・ペテルブルクで、上流階級の患者を “チベット医学 “と称して治療し、頭角を現していた。おそらくバドマエフは、アレクシスのだまされやすい両親に、ラスプーチンが奇跡の人であると信じ込ませるように、薬を塗ったり止めたりしたと思われる。
このような考え方は、皇室が非常に孤立していたおかげで頭角を現したのだ。アンナの第一の忠誠心はラスプーチンではなく皇后にあったことを当時理解する人は少なかっただろう。また、バドマエフとラスプーチンは、農民の宮廷生活の初期には、味方ではなく敵同士であったことも事実である。さらに重要なことは、血友病の偽の発作を引き起こす薬を誰も特定できなかったことである。
ラスプーチンは催眠術を使ったと多くの人が推測している。皇室の子供たちの英語家庭教師であったチャールズ・シドニー・ギブスは、ラスプーチンの成功の秘密は催眠術にあると考えた。歴史家のジョージ・カトコフは、催眠術は “血管運動系に影響を与え、アドレナリンや同様の薬物の効果に匹敵する血管の収縮を引き起こす “と考えていた。彼は、ラスプーチンの「治療」は、発作の時に少年を落ち着かせる能力によるものだと考えていた。
マリア・ラスプーチンは、父親が催眠術を “悪魔的 “なものとみなして、無関係だと主張した。彼女は間違っていた。 これは彼女がいかに父親を理想化していたかの典型的な例である。事実、ラスプーチンは一時期、催眠術の研究に非常に興味を持っていた。1913年、オクラホマは一流の催眠術師からの手紙を傍受し、ラスプーチンが教えを乞いに来たところだと愛人に告げた。その指導が実現する前に、警察はその家庭教師になろうとする者を首都から追放した。しかし、ラスプーチンはその後も探求を続け、1914年には護衛から、彼がジェラシム・パパンダートという人物に催眠術を習っていると報告された。しかし、ラスプーチンは1906年に祈りによってアレクシスを癒すようになった。
ラスプーチンがアレクシスに催眠術をかけるのを目撃したという人がいないのは興味深い。ニコライとアレクサンドラはある意味で鈍感だったが、きっと彼ら(または誰か)は男が自分の息子にそんなことをしていたなら、気づいただろうし、それをありがたく思ったことだろう。ラスプーチンは時々、その場にいなくても若い患者を治すことがあった。おそらくそれは自己暗示の産物だったのだろう。ある時、アレクシスが発作に苦しんでいると、電話でラスプーチンが宮殿に呼び出された。彼は酔っぱらっており、その状態で現れるのは賢明でなかっただろう。ラスプーチンはその電話で、出血は1時間以内に止まると予言し、止まらなければ行くと約束した。ラスプーチンの予言通りに回復した。
アレクシスは間違いなく、ラスプーチンの強烈な個性に支配されていた。ニコライの妹のオルガは、ある晩、アレクサンダー宮殿でそれを見た。皇子はウサギのふりをして、部屋の中で飛び跳ねたりしていた。そして、まったく突然、ラスプーチンは子供の手を捕まえて寝室に連れて行った…. . . まるで教会にいるような静けさがあった.. . 子供たちは大男のそばにじっと立っていた。大男は頭を下げていた。「私は彼が祈っていたことを知っていました。それはとても印象的でした。そして、私の小さな甥が大男の祈りに加わっていることも分かりました。そのとき、私はこの人が誠実な人であることを悟ったのです」。
ラスプーチンの存在感、整然とした話し方、宗教的な激しさのオーラ、これらすべてが混乱した状況を落ち着かせたことだろう。アレクサンドラの態度は重要であった。彼女は最初からラスプーチンが息子を癒すことができると確信しており、彼の存在と祈りが回復につながると考えていた。それを信じることで、彼女は心が楽になり、その確信をアレクシスに伝えたに違いない。彼のストレスが軽減されれば、出血が止まり、自然治癒が促進されたかもしれない。しかし、このことはラスプーチンの初期の成功の説明にはならない。ニコライとアレクサンドラには奇跡を期待する理由がなかったのだ。アレクシスに関しては、1906年にラスプーチンが初めて枕元に来たとき、彼は2歳で意識不明だった。そのような状況で催眠術が有効であったとは考えにくい。
ラスプーチンの幸運は偶然の一致によるものだとする説もある。ピエール・ジリアールは、アレクサンドラが「ある偶然の一致」をラスプーチンの奇跡としてとらえたと考えた。皇后の侍女の一人であるソフィー・ブクショーヴェデンも同様に、ラスプーチンの成功は幸運なタイミングによるものだとした。彼女は、ラスプーチンには「情報源」があり、皇子の回復が「彼のおかげであると思われる」ちょうどよいタイミングに現れることができたと考えていた。ブクショーヴェデンはおそらく共犯者としてアンナ・ヴィルボヴァを念頭に置いていたのだろう。アレクサンドラの友人の一人であるリリ・デーンは、ラスプーチンの治癒は「偶然とさらなる偶然だけ」によるものだと主張した。この確信はニコライの母マリア・フョードロヴナや従兄弟のミハイロヴィチも同じように考えていた。
ラスプーチンの成功のいくつかは偶然の一致で説明できるかもしれない。確かにラスプーチンが現れた瞬間にアレクシスが回復していたこともあったが、多くの場合そうであったはずがない。また、ラスプーチンが宮殿に協力者を置いていたという話も説得力がない。アンナはこのような方法でアレクサンドラを欺くことに同意したはずはなく、そのような示唆は二人の友情を失わせることになる。ラスプーチンはまた、そのキャリアの初期において、偶然の一致に頼ることはできなかったはずである。
ソフィー・ブクショーヴェデンの幼少時代のある出来事が、別の考えを呼び覚ます。彼女は、ある人々が “zagovarivat’ krov'”(血との交渉)と呼ばれる才能を持っていることに注目した。彼らは一般に動物を助けるが、時には人間を治療することもあった。ブクショーヴェデンは、自分の領地の馬が趾をひどく切ったとき、「馬の囁き師アレキサンダー」が呼ばれたと回想している。農民は包帯をはずし、誰も解読できない言葉をつぶやきながら傷口をマッサージした。すると出血が止まり、馬は元通りになった。また、ある貴族は、木を切っている最中に斧が滑って、足を切断しそうになったことを記録している。誰かが、ある農夫を連れてきた。その人が来て祈ると、急に血が止まったというのだ。
ラスプーチンが若い頃、馬に特別な理解を持っていたという話から、ブクショーヴェデンは、”血との交渉 “のような力を引き出したのではないか、と考えたのだ。しかし、人間の経験には、理屈だけでは説明できない部分があるのも事実だ。ロシア正教会は現代でも奇跡が起こると教えており、ある種の聖像には病人を癒す力があるという可能性を受け入れていた(現在も受け入れている)。もちろん、ラスプーチンの敵は、ラスプーチンが霊的な能力を持っていたとか、皇子を治療するためにそのようなものを使ったという考えを断固として否定している。
ラスプーチンは奇跡を起こすとは言っていない。彼は自分の治癒は神の意志の現れであり、神の恵みであると主張した。”この世に聖人はいない “と彼はよく言っていた。 “人は生きている限り、罪を犯す”。ニコライとアレクサンドラは彼をこのように見ていた。 ラスプーチンは聖人ではなく、息子の命を守る霊的な才能を持った男だと。ラスプーチンは神が用いた彼らの家族全員を保護するための仲介者であった。その力を持っていたのは神であった。
アレクサンドラは、正教会の神秘的な要素を積極的に取り入れたため、一般の信者は不安になった。彼らは、皇后を極端で狭量な人物と見なした。また、彼女の態度はラスプーチンへの信仰と関係があることも感じ取っていた。ニコライはもっと理性的で、妻の情熱を受け入れて家庭の平和を守る夫のような人であった。しかし、彼はラスプーチンが神の人であると確信していた、特にスパラの後ではそうであった。アレクサンドラとその夫にとって、事実は明らかであったろう。アレクシスは死の淵に立たされ、ラスプーチンが現れて祈り、息子は回復したのである。皇帝夫妻は、その1912年の秋にスパラで奇跡が起こったと確信した。この体験は、二人をさらにラスプーチンに近づけた。仕方なくという感じだったのだろう。懐疑論者の戯言と息子の命とどちらが大事なのだろうか。このような状況下での出来事であったため、彼らにとって決断は難しいことではなかった。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』11
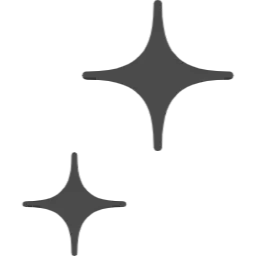
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

