鼻のない女
1914年の春、ニコライ2世は突然ラスプーチンに反旗を翻し、彼の帰郷を強要した。この劇的な展開の理由は、出来事そのものに説明がつくものの、完全には明らかにされていない。
ニコライ2世は、ラスプーチンを民衆の声として受け入れ、対話から活力を得ていた。彼は祈りの力を信じ、奇跡が起こる可能性を受け入れていた。ラスプーチンには霊的な才能があることを経験的に確信していたのである。しかし、皇帝はロシアの支配者としての権威から、妻が常に政治問題に友人を介入させることに憤りを感じていたのであろう。バルカン半島で再び紛争が起こっていることは誰もが知っていた。ニコライは妻と農民がまだ戦争に反対していることを知っており、戦争を避けようとする彼らの終わりのない圧力に憤慨していたかもしれない。1914年3月14日、ラスプーチンが皇族と会見したとき、アレクサンドル宮殿の緊張は明らかに高まりった。ニコライはシベリアの神秘主義者でありヒーラーであるラスプーチンに首都を去るように命じた。この騒動の直後にレオニード・モルチャノフが訪ねてくると、旧友のラスプーチンは予想外の展開に「非常に動揺していることが分かった。「ラスプーチンはこう言った。「悪いことだ」ラスプーチンはこう説明した。「突然だが、私は自分の町ポクロブスコエに帰らねばならなくなった」。
ラスプーチンの父エフィムは、偶然にも息子を訪ねてきており、二人は一緒にチュメニまで旅をすることになった。新聞はラスプーチンが美しい毛皮のコートとビーバーの帽子をかぶっていることに注目したが、彼がサンクトペテルブルクから追放されることは知らなかった。ニコライ2世がこの決断を下すにあたり、妻に立ち向かったことは明らかであり、そうすることで妻がそれを受け入れたことは興味深いことである。アレクサンドラがラスプーチンと別れるときに自分の私室から渡した7万5千ルーブルは、別れの贈り物、つまり彼女と農民の関係をできるだけ気持ちよく終わらせるための親善の品であったのだ。
しかし、皇后はそのような場合でもあきらめなかった。これが物語の後半部分である。1914年5月、ラスプーチンは首都に帰ってきた。アレクシスが突然ラスプーチンを必要としたと思われるが、後の出来事から、皇帝が譲歩して、農民を公事に関与させないという協定を得たと思われる。ニコライの日記には、5月18日と6月17日にラスプーチンが皇帝夫妻を訪問したことが記されている。3人の旧友は、ラスプーチンが最近戻ったことで、単に不幸な誤解が解けたかのように振る舞ったのだろう。
ニコライとアレクサンドラは、1914年6月のルーマニアへの公式訪問を皮切りに、忙しいスケジュールをこなした。帰国後、ザクセン王を歓待し、6月20日、イギリス第一戦艦隊がサンクト・ペテルブルクに錨を下ろし、10日間滞在した。7月下旬には、フランス大統領レイモン・ポアンカレが待望の国賓訪問を果たした。皇帝夫妻は、ラスプーチンがポクロフスコエで夏を過ごすために出発する直前の6月17日火曜日に、ラスプーチンを迎え入れた。その日はグレゴリオ暦で6月30日、その2日前にブラックハンドのメンバーがサラエボでフランツ・フェルディナント大公夫妻を殺害した日である。ラスプーチンも含めて、この暗殺が戦争につながるとは誰も思っていなかった。実際、この農夫はシベリアへ旅立つ直前、記者にこの悲劇について感想を述べた。
「私の農民的な考えでは、これは大きな出来事で、ロシア人とイギリス人の友好の始まりだと思う。イギリスとロシア、そしてフランスとも友好を結ぶことができれば、それは、強力な力となり、実に素晴らしいことだ」。
1913年のバルカン危機の際にラスプーチンが吐露した「ロシアの偉大さ」についての暴言はなくなったわけだが、それはおそらく、彼をサンクト・ペテルブルクに連れ戻すための妥協案の一つであったのだろう。今度は、ラスプーチンがいかに同盟国を大切にしているかを世界に訴えていた。今回、シベリアの神秘主義者でありヒーラーである彼は、王室の主人を困らせることはしなかった。
オーストリアは、セルビアが「ブラックハンド」を支援していたことを理由に処罰しようと動き、2週間にわたって外交的緊張が高まった。セルビア人はロシアに支援を求め、ドイツはオーストリアを支持した。フランスは、今度はロシアの側で戦うと明言した。局地的な戦争は過去のものとなる。オーストリアがセルビアを攻撃すれば、ヨーロッパ全体の紛争に発展する。
アレクサンドラはラスプーチンに緊急電報を打った。「重大な事態です、戦争の脅威が迫っています」。電報はグレゴリオ暦7月13日(新暦6月29日)の午後3時前にポクロフスコエに到着した。使者はそれを急いでラスプーチンの家に運んだ。ラスプーチンは彼にチップを渡すと、読みながら家に入ろうとした。だがすぐに、その使者を止め、返事を書き記した。ラスプーチンは、「私が家の門から通りに出たとき、見知らぬ女性が家の垣根の左側から近づいてきた」と回想している。口と顔はベールで覆われていて、目しか見えなかった。名前も知らない。彼女が物乞いだと思い、ラスプーチンはポケットから小銭を取り出した。「その時、彼女の手に短剣が光り、私の腹、臍の近くに一度だけ刺さった。そして、私の体から血が流れ出るのを感じた」唖然としたラスプーチンは振り返り、両手で傷口を押さえながら教会に向かって走った。女は短剣を持って私の後を追った。ラスプーチンの叫び声を聞いた群衆が、加害者がもう一撃を加えるのを防いだ。
ラスプーチンは大量に出血しながら自宅まで運ばれた。チュメニへの電報でウラジミロフ博士と2人の助手が急行した。ウラジミロフは、夜中にポクロブスコエに着いたら、「ウォッカをやるから」といって、運転手を急がせた。そして、8時間かけて目的地に到着した。看護婦は「ラスプーチンが羊の皮のコートで覆われ、タオルにくるまってベンチに横たわっているのを見つけた」と回想している。傷は長さ2センチ、幅1センチで、腸は傷ついていなかったが、容態は深刻で、医師は家族に「死ぬかもしれない」と警告していた。手術は家の中で、ろうそくの明かりで行われた。マリア・ラスプーチンは、父親が麻酔を拒否したことを思い出した。ラスプーチンは、自分は助かると言い張り、医者に心配しないようにと言った。そして彼は気を失った。ラスプーチンは意識が戻ると司祭を呼び、最後の告解を聞いてもらった。
ラスプーチンはアレクサンドラにも電報を打ち、「あの腐った塊にナイフで刺されたが、神の助けで生きられる」と伝えた。ラスプーチンはアレクサンドラからの返信が届くころには意識が遠のいていた。「私たちは深く動揺しています。心から祈っています」。7月2日、彼女はこう書いた 「私たちの悲しみは筆舌に尽くしがたいものです。 神のご加護を願っています」。ラスプーチンの医療を監督するため、一流の医師がシベリアに派遣された。ニコライ2世はまた、内務大臣にラスプーチンの警備を今後最優先させるよう指示した。
「あの女に腹を刺されたが、それほどひどくはない」 ラスプーチンは別の電報で皇后に断言した。「奇跡によって救われた。私は皆のために生きる。 聖母の涙は無駄ではなかった。医者を呼んでくれたんだ」 7月3日までに彼は十分に安定し、移動できるようになった。ラスプーチンは、プラスコバヤとマリアと一緒に蒸気船ラストーチカ号でチュメニに運ばれ、宮廷医が国立病院で彼の治療を指揮することになった。ラスプーチンは、到着した時には意識が混濁していたが「乗り越えてみせる!乗り越えてみせる!」と繰り返していた。ラスプーチンはその夜も電報を送り、アレクサンドラに次の手術が迫っていることを警告した「かなり深刻な事態になるだろう。3週間は寝込むことになる」と。ラスプーチンは実際には46日間入院していた。
翌朝、医師は手術をして、内部の損傷を修復し、傷口を縫合した。すべて順調で、医者はラスプーチンに、おそらく2週間以内に退院できると告げた。その後、彼の体温は39度まで上昇し、数時間後に下がった。電報で皇后にその経過を報告し続けた。7月7日、ラスプーチンはアレクサンドラに「抜糸は問題なかった、回復するだろう」と告げた。7月12日には一転して「今日は大量出血で入院が長引きそうだ」と言い出した。その後、彼は立ち直ったが、次のように告白した。 「実は非常に危険な状態で、失血はひどく、悪臭はひどいものでした」。
当時のラスプーチンのスケッチが残されている。そこには、死に直面しながらもかろうじて生き延びた男の姿が描かれている。ラスプーチンは頭を下げ、手を組んでいる。彼自身の手による銘文にはこうある。”明日はどうなるのだろう?主よ、あなたは私たちの道しるべです。人生でいくつの試練を乗り越えなければならないのだろう? 国の各地から手紙や電報が届き、心配の声が上がった。アキリーナ・ラプチンスカヤは信者からの贈り物を持ってシベリアに急ぎ、ラスプーチンの枕元で看病することにした。ヴァルナヴァ司教が訪れ、さまざまな女友達も訪れた。
ラスプーチンには証拠がなかったが、イリオドールが手を回したの犯行と確信した。彼はイリオドールが「異常」であることを警察に話した。
『彼は神から、聖なる教会から切り離れている。私は4年前、ツァーリツィンでイリオドールと一緒だった。私は彼と友好的に暮らし、私の考えをすべて彼と共有した。私は彼を助けていたが、支援を止めたとき、彼は私に敵意を抱き始めた。私たちの不仲の原因は、私がヴォルガ川の巡礼をさせなかったことと、彼の新聞に金を出さなたったことだ。イリオドールは4年前にポクロブスコエで、重要な手紙を盗み、それを敵に渡したのだ。これ以上は言うことはない。』
ラスプーチンは一時は体調が回復し、病院を休んでトボリスクを訪れることができるようになった。彼は蒸気船で移動し、ヴァルナヴァ司教の歓迎を受け、船上で聖歌をささげた。船内はラスプーチンが死にかけたという噂で持ちきりだったが、警察は好奇心の強い人々を彼の船室に近づけないようにした。時々、女性のファンが “パパ “に何か持ってこようと現れた。ラスプーチンは彼女たちにコルセットを着用しないように命じたが、それはすぐに船内に広まった。ラスプーチンがチュメニに戻ったとき、埠頭で待っていた多くの群衆は不思議な光景を目にした。ラスプーチンは、女性の白いロングドレスとそれに合うボンネットを身にまとって船から降りた。
ラスプーチンの存在は、国立病院の眠ったような日常を混乱させた。ある新聞は “農民や知識人の崇拝者がジャーナリストやカメラマンと一緒に来ている。しかし、患者を見たのは家族とごく近い知人だけだ。彼らは、ラスプーチンがジャーナリストやカメラマンを大砲が撃てる範囲に入院させないように要請したと言っている “と述べた。ラスプーチンの支持者は、好奇の目を避けるために彼を個室に移すよう求めたが、この悪名高い患者に苛立った病院の管理者は、この要求を拒否した。
ラスプーチンの襲撃は、マスコミの新たな注目を浴びるきっかけとなった。ラスプーチンの経歴、教え、信奉者、恋愛、「高名な人物とのつながり」(ロシアの新聞で突然よく使われるようになった言葉)についての記事が突然掲載されたのである。ラスプーチンが大衆の心を掴んでいることを雄弁に物語るものだった。また、ラスプーチンは、このような記事の多くに見られる不正確さや偏見に憤慨していた。
検閲は、ジャーナリストがラスプーチンの名前を皇室の一員と結びつけてはいけないとしたが、報道機関はラスプーチンを論じる自由を享受していたことは注目に値する。”強大なロシア帝国の全権限は” “グレゴリー・ラスプーチンの前にひざまずいている “と『Voice of Moscow』は読者に伝えた。またサンクトペテルブルクの「クーリエ」紙は読者に次のように伝えた。
『ラスプーチンは性的な問題で正常ではないという噂がペテルブルグで流れている。我々の仲間はこの問題を明らかにするために女性医学研究所のクルネフ教授に話を聞いた。教授は、性的不満足は女性の間で「非常によく」起こるが、男性の間でも「まれではない」…彼らが完全に成長した大人になるのは、40歳を超えてからである、と話した。「私や多くの医師は、これらの病気を心理的、神経的障害と見ている。この病気は、病人にとって非常に危険であり、治すのはかなり難しい。長く頑固な闘病生活が続くのが普通である。隔離が望まれることが多い」。』
『スピーチ』編集長は「ロシアは無限の可能性を秘めた国だ。それにしても、下級役人から大臣に至るまで、あらゆる階層の指導者たち、しかもヒステリックな女性やお調子者の役人だけでなく、知的で新聞を読む幅広い層の人々が、ラスプーチンに与えている意義は受け入れがたい」と示した。
その日の午後、ポクロブスコエで起きた襲撃事件についての報道は、かなり想像力に富んだものだった。ある新聞はラスプーチンの言葉を引用している。「私は木の棒をつかんで、いつ彼女の頭を割ろうか と考えていた。それから、彼女がかわいそうになって、肩を軽く打ったんだ。彼女は倒れ、人々は彼女の腕を掴み、引き裂こうとした。私は彼女のために立ち上がったのだが、力が及ばず、倒れてしまった」。ラジンスキーとネリパは、この話を素直に受け止めている。しかし、警察の報告書やその他の資料から、当時、ポクロブスコエに流れていたうわさをもとに、ジャーナリストたちが空想に満ちた話を大量に捏造していたことがうかがえる。
ラスプーチンを助けるために駆けつけた群衆は、加害者を警察に引きずり込んだ。彼女は誰かに突き飛ばされ、左手首を切ったが、それ以外は無傷だった。警察は、地区行政ビルの部屋で容疑者を取り調べた。彼女は、レーニンやケレンスキーを生んだシンビルスク州出身の33歳の未婚女性、キオニヤ・クズミナ・グセバであることが分かった。姉と一緒にツァリーツィンに住み、お針子や召使として働いていた。警察は、グセバを「ほとんど読み書きができない」「正教徒で、何の財産も持っていない」と説明した。逮捕した警官が「異常な特徴」の欄に、「鼻がなく、その代わりに不規則な形の穴があいている」と書いている。
グセバは、イリオドールへの忠誠心に駆られていた。警察は彼女を、ツァーリッツィンでのイリオドール信奉者の輪がどんどん狭まっていく「単純で、教育を受けていない、未熟な労働者」の一人であると評した。警察はグセバを厚遇し、市長の妻はグシバの身の回りの世話をしてくれた。グセバは、イリオドールと同様に自分もラスプーチンを憎んでいたという。彼女は、使用人兼お針子として毎日稼ぐ6ルーブルを誇りにしていた。この金額を微々たるものだと思う人もいるかもしれないが、「小さなお父さん(イリオドール)には何か食べさせなければならない」と言って、喜んで共同基金に寄付した。
グセバはラスプーチンと接触したことはなかったし、彼を暗殺する計画は完全に彼女のものであると断言した。新聞は彼女の言葉を借り、ラスプーチンが”浪費家で偽預言者 “であると説明していた。彼女は列王記上18章40節を読んだ日のことを思い出した 。それは1914年5月18日だった。そして、それが自分がしなければならないことを悟るための力強い喚起であることに気づいた。エリヤが450人の偽預言者の喉を切り裂くのを正当化したのなら、グセバがたった1人殺したところで、誰も異議を唱えないだろう?卑しく、醜い姿のグセバは、ラスプーチンを抹殺することで、イリオドールの世界に自分だけの居場所ができると思っていたのだろう。この怪物を世界から排除するために誰かが犠牲にならなければならないのなら、それは彼女であって、若くて美しい、将来が期待できる人ではないのだ。
グセバが選んだ武器は、彼女がいかに殺人に関して無知だったかを示していた。女性が至近距離で効果的に使える中型の刃物ではなく、男性が握れるように設計された白骨の柄を持つ15インチの短剣を選んだのである。グセバはこの扱いにくい刃物で、ヤルタからサンクト・ペテルブルグ、ポクロブスコエまで獲物を追いかけた。そこで彼女は部屋を借り、家主に “霊能者 “に会いに来たと言った。警察は、ラスプーチンの家がよく見える場所にある地区管理ビルの階段で、グセバが何度も目撃されていることを知った。
グセバは、イリオドールとは無関係と主張したが、警察は警察は疑心暗鬼になった。グセバが主張する39ルーブルで、帝国を横断する旅ができたというのは、彼女の主張通り4等車に乗っていたとしても疑わしい。彼女が逮捕されたとき、まだ10ルーブルを持っていた。グセバは饒舌で反抗的だった。謝罪を拒み、ラスプーチンがまだ死んでいないことを知り、死を望んでいることを認めた。
彼女の尋問者は、心神喪失を主張するように、あるいは「宗教的エクスタシー」の苦しみの中にいることを主張するようにと誘った。彼女は、そのような主張が自分の罪を軽減し、軽い罰をもたらすかもしれないことを理解していたのだろう。しかし、彼女は完全に道理をわきまえていると主張し、またそれを疑う余地はない。
地元の刑務所に収監されたグセバの独房に、新聞記者たちが押しかけた。記者たちはすぐに彼女を尊敬するようになった。「聖地を数多く訪れ、さまざまな人と交わった」ことから、「多くを見聞きし、知識と教養ある女性」であることがわかる。グセバは非常に信心深い女性である。
その1人が、サンクトペテルブルク・クーリエ紙の記者ベンジャミン・デビッドソンである。彼は、事件の前夜にポクロブスコエに出没した理由を説明できないので、警察は彼を追放しようとしたが、首都の上司がこれを拒否した。噂によると、チュメニの協力者がデビッドソンに到着する時間を教えたという。デビッドソンは、このときグセバとの対談を準備していたというから、警察の上層部がこの計画を知っていて、このままではまずいと思ったのだろう。デビッドソンの追放という初歩的な措置は、地元警察の努力で打ち消された。この「お偉いさん」、あるいはその部下が、事件の前からデビッドソンにストーリーの準備をさせていたらしい。
グセバに関する話を捏造したのは、デビッドソンだけではなかった。新聞に掲載された不正確な記述は、歴史家を混乱させた。例えば、ラスプーチンとグセバが恋人同士であったが、彼女を不当に扱ったので、復讐したのだということだが、事実ではない。ラスプーチンとグセバが初めて会ったのは、彼女がラスプーチンを襲った日だった。ラスプーチンがツァーリツィンのバラシェフスカヤ修道院の若い美しい修道女クセニアを犯したため、グセバが怒ったという報道はどうだろう?確かに修道院にはその名の修道女がおり、彼女はイリオドールを慕っていると告白している、つまりラスプーチンが嫌いだったのだろう。しかし、クセニアは裁判所の供述書で、ラスプーチンを見たのは2回だけで、2回とも遠目だったと明言している。彼女はこの農夫と良い経験も悪い経験もなかった。
グセバの鼻の欠損は謎を深めた。ジャーナリストや歴史家は、このひどい醜形は梅毒によるもので、彼女はラスプーチンからこの病気をもらい、復讐しようとしているのだと考えた。しかし、グセバは、13歳の時に薬の副作用で鼻を失くしたと主張した。
また、ラスプーチンがグセバに同情を示したとか、彼を救おうと群がる村人から彼女を守ろうとしたというのも俗説である。ラスプーチンは彼女を “私の尻にナイフを突き立てた淫乱女 “と呼んだ。彼は激怒したが、ラスプーチンは見ず知らずの人間がなぜ自分を殺すほど憎んでいるのかを世間に知られることは自分の利益にならないと感じていた。ラスプーチンは彼女を裁判にかけることを望まなかった。警察が「1914年6月29日の犯罪」と呼ぶイリオドールに対する証拠がないため、裁判所はグセバにのみ訴訟を起こすことができた。医師たちは、彼女が「責任能力がない」のであり、刑事罰や裁判を免れるべきだという結論に達した。チュメニ地方裁判所は、グセバは事件当時「精神異常」であり、「宗教的・政治的な思想の影響により情熱的な状態にあり、現在もその状態が続いている」と断じた。裁判長は、グセバを「回復するまで特別な精神科施設に入院させる」よう指示した。
グセバは、トムスクの精神病院へ送られた。同じ目的地に向かう他の患者たちと話をしないように、彼女は特別な船で移動し、別の船で他の患者たちを運んだ。裁判所は、「少なくとも2カ月間」の監禁を命じた。医療施設に収容されたものの、他の患者とは隔離され、囚人のような扱いを受けた。この間、グセバは、慈善事業としてショールを縫う許可を得ようとしたが、当局に拒否された。
犯行から8ヵ月後のグセバの精神鑑定では、「錯乱した考えや幻覚」「特定のタイプの心神喪失の症状」は見られないことが認められた。彼女は単に反社会的で、人と喧嘩したり、「根拠のない不満」を追求したりする「ヒステリックな性質」を示していたのだ。主治医は、これらの症状は、より良い施設に移せば、恐らく落ち着くか、「特に急性には現れないだろう」と考えていた。妹は二度にわたって釈放を求めたが、当局は拒否した。1917年2月、ツァーリ政権に代わる政府の法務大臣ケレンスキーの直筆の許可で、グセバはようやく釈放された。そして、簡単な供述をした後、歴史の表舞台から姿を消した。
ラスプーチンは1914年8月17日に退院した。ヨーロッパが戦争に突入したその重要な夏はサンクトペテルブルクを留守にしなければならなかった。しかし、電信によって、彼はますます心配になる皇后と常に連絡を取り合っていた。「まだ戦争は起こっていないし、起こさなくてもいい」とラスプーチンはチュメニから電報を打った。毎日の新聞報道から、ツァーリが直面する複雑な状況を想像した。そしてニコライに、ロシア国内の「混乱」を隠すことが重要であると警告した。(ラスプーチンは、ロシアがドイツと戦争になったら大変なことになると知っていたことだろう)。翌日、ラスプーチンは「一緒にいられないのが残念だ」と言い、7月1日には「すべては過ぎ去る」と約束し、「われわれはただそれを乗り越えなければならない。しかし、(敵に)再び叫び出す理由を与えてはならない」とした。
「悪い知らせです」アレクサンドラは7月3日、ラスプーチンに言った。「恐ろしい瞬間です。私たちのために祈ってください、私には他の人たちと争う力がありません」。同じ日、ラスプーチンはニコライに言った「戦争のことはあまり心配しないでください。もうすぐ奴らの胸にクソを投げ込むことになるが、まだだ。その時が来れば、我々の苦しみは報われるだろう」。3日後、ラスプーチンは皇帝に電報を打った「私は平和と平穏を信じ、願っていますが、彼らは大きな悪を計画しています。あなたの人生の一部である私たちは、あなたの苦しみをすべて理解しています。顔を合わせないのはとてもつらいことです。心の近い者たちは密かに思っているのです。”どうしたらあなたを助けられるのか “と」。
ラスプーチンは、アレクサンドラが平和が失われつつあることに絶望していることを理解し、その思いを共有した。彼らの最大の悪夢であるドイツとの戦争は目の前で展開され、それを止めることはできなかった。元首相のセルゲイ・ヴィッテは、ラスプーチンこそが「現在の複雑な政治状況を解くことができる」唯一の人物だと考えていた。「ラスプーチンはロシアの精神、状態、歴史的な志を誰よりもよく知っている」とヴィッテは主張した。「しかし、残念ながら、彼は今ここにいない」。
噂によると、ラスプーチンはロシアが軍隊を動員しようとしていることを新聞で知り、包帯を破ってしまったという。日々の電報では危機を打開できないと考えたラスプーチンは、後に「特別電報」として知られるようになるものを皇帝に送った。彼はこの電報をアンナ・ヴィルボヴァを経由させ、迅速な配達とその見解の弁明を確保した。原文は失われてしまったが、ヴィルボヴァは「パパに戦争を計画させないでください。戦争はロシアとあなた方の終焉を意味し、あなた方はすべてを失うでしょう」と書いてあったと回想している。アンナは、この “ラスプーチン側からのほとんど前例のない国政干渉 “に皇帝が激怒したと述べた。ニコライは「我々の内政は他人の影響を受けるものではない」と主張し、ラスプーチンを反逆罪で裁判にかけることを口にした。
さらに皇帝は、警察がラスプーチンの電報を傍受し、ラスプーチンと彼の平和主義を貶めようと、それを下院の主要議員にリークしたことを知り、苛立ちを募らせた。ラスプーチンは後に友人に、「あの電報のせいで、敵は私を裁判にかけようとした」と語っている。皇帝は農民の友人を擁護し、少なくともラスプーチンの批判が的外れであることを明らかにした。皇帝は「これは我が家の問題であり、法廷の問題ではない」と主張した。しかし、今回のリークのおかげで、「特別電報」の内容に関する別の説明が可能になった。ケレンスキーは当時、下院議員であった。彼はその文書を見て、「宣戦布告はするな、ニコラーシャ(西方ロシア軍の好戦的な司令官)をクビにしろ」と書いてあったと回想している。宣戦布告をすれば、あなたとツァレヴィチの上に災いが降りかかるだろう」と書かれていたのを覚えていた。
ニコライ2世は、この7月という時期に揺れ動いた。自分の直感、アレクサンドラの懇願、ラスプーチンの和平への主張、そして最後に官僚や将軍たちからの軍隊を動員して戦争に備えよという圧力、相反する力の狭間に立たされていた。アレクサンドラは、夫が動員を許可したことを知ると、当時の人々は、これは先制攻撃の一歩手前だと考え、愕然とした。「戦争だわ!」彼女はアンナにつぶやいた。「知らなかった。もう、何もかも終わりだわ」。
1914年8月1日、ドイツがロシアに宣戦布告した。(ニコライ2世は翌日、自ら宣戦布告し、冬宮に大群衆を集めた。午後3時過ぎ、ニコライがバルコニーに現れ、それに続いて皇后も現れた。民衆の間に大きなうねりが起こり、「万歳!」の声が響き渡った。臣下たちはひざまずいていた。前列にいた人々は、ニコライに話をさせるため、他の人々をなだめようとしたが、興奮はおさまらない。しばらくして、彼らはロシア国歌「神よ、皇帝を護り賜え」を歌い始めた。
それは感動的な光景だった。ニコライ2世と彼の国民がついに一つになったのだ。これは決定的な瞬間であり、未来を直接指し示すものであった。もし、ロシアが勝利すれば、歴史はニコライの治世における暗黒の瞬間、すなわちホドゥインカ原、日露戦争、血の日曜日、それに続く民衆の反乱の弾圧を許すだろう。もし、彼が失敗したら?ロシア人はそのことを話したがらないが、その可能性は楽しい宴席の亡霊のように背後に漂っていた。その時、指導者はバルコニーに立ち、眼下の広場に溢れる愛国心を味わっていた。この感動的な瞬間が、数ヵ月後に「ラスプーチンの治世」になると誰が予想しただろうか。ラスプーチンでさえ、そんなことは考えもしなかっただろう。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』13
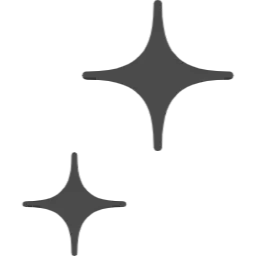
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

