3 ニコライとアレクサンドラ:友を待つ
1881年のある寒い日、ロシア最後の皇帝となる運命の少年は、自らの運命を垣間見ることになる。3月最初の日曜日、サンクトペテルブルクには一面の雪が降り積もり、太陽の下でアレクサンドル2世の馬車が凍った通りを疾走していた。その時、馬車の行く手に突然爆弾が投げ込まれ、爆発は地面を揺るがし、窓はガタガタと音を立て、火と煙が空に向かって巻き上がっていった。アレクサンドルは怪我をしなかったが、負傷者を気遣って現場に留まった。もう一人の男が放った砲弾は、皇帝の足元で爆発した。アレクサンドルは最後に「宮殿へ、そこで死ぬ!」とつぶやいた。
皇族の一族が冬の宮殿に駆けつけた。12歳のニコライは、暗赤色の血の跡を追って皇帝の書斎に向かった。祖父は意識不明で、ひどい顔色をしていた。右足はなく、左足は粉々に砕け、腹は血にまみれ、顔は榴散弾で引き裂かれていた。医師は何もできない。
革命家たちが皇帝を憎んだのは、アレクサンドル2世がロシアを改革するために多くのことを行ったからであり、皮肉なことであった。1860年代に農奴を解放し、裁判所を近代化し、選挙で選ばれた地方政府という新しい制度を作ったのである。しかし、自由主義者、学生、駆け出しの革命家などの知識層は、これらの改革を臆病で中途半端な譲歩であり、真の改革を回避するためのものであると考えた。不満の高まりは皇帝をさらなる改革から遠ざけ、皇帝の敵は暴力に走った。3月11日の出来事は、困難な状況の産物であった。
アレクサンダーの寝室での恐ろしい光景は、ニコライを震撼させた。後にロシア最後の支配者となる少年は、次のように告白している。「私は恐ろしい試練を受ける運命にあるという予感、密かな確信さえもがある。そして、私の報いはこの世にはないのだ。私が恐れるものは私を不意に襲い、避けようとするものは私の頭に降りかかる」。
ニコライ2世の誕生日は1868年5月6日で、正教会が旧約聖書の総主教ヨブを祭る日である。宗教心が強く、神秘主義に傾倒していたニコライは、自分に降りかかる試練を神の意志として受け入れていた。不機嫌で威圧的な父親と、母親のマリア・フョードロヴナによって甘やかされて育ったニコライは精神的に未熟で、自信もなかった。1894年、アレクサンドル3世の早すぎる死によって、ニコライは王位についた。「どうしたらいいんだろう」と、ニコライは従兄弟で義兄のアレクサンドル・ミハイロビッチに泣きついた。「私やあなた、そして家族はどうなってしまうのだろう?私はツァーリになる準備ができていない。ツァーリになる覚悟もないし、なりたいと思ったこともない。統治という仕事は何も知らないんだ」。
自信喪失は当然であった。ニコライ2世は、ハンサムで礼儀正しく、洗練されたマナーと外国語の才能に恵まれた人物だった。しかし、ロシアを統治することを考えると、彼の教育は行き当たりばったりであった。家庭教師は採点することも、質問することも許されなかった。新皇帝は聡明で頭の回転が速かったが、批判的な分析をする才能はなかった。ニコライの父は、即位するわずか1年前に、彼を「全くの子供」「幼稚な判断力で、本能と感情に支配された子供」と呼んだ。確かにニコライは、王位に就いてから成長し、勤勉で義務に忠実な、狂信的ともいえる性格になった。しかし、その反面、衝動的で、忠告を無視した単独の決断が目立った。
ニコライは、神が自分にロシア帝国を統治するよう命じたと信じていた。1613年にロマノフ家の初代皇帝ミカエルを選出したのが民衆議会であったとしても、独裁的な政治体制がロシアの偉大さの基盤であったと確信していた。ある廷臣は、ニコライ2世は「自分の高貴な地位には天罰が下るという揺るぎない信念を持っていた」と述べている。「彼の使命は神から発せられたものだ。自分の行動は、自分の良心と神に対してのみ責任がある」と。彼は、市民の自由や議会はロシアにとって異質なものだと考えていた。ニコライは「代表制の政府には決して同意しない。神が私に託した民衆に害を及ぼすと考えるからだ」と誓った。
レフ・トロツキーは優れた歴史家であったが、ニコライ2世に対する評価は極めて否定的であった。このボルシェビキの指導者は、最後のロマノフが「帝国と革命」を受け継いだが、「地方や郡を統治できるような資質は一つもない」と書いている。公平かどうかは別として、世界最大の国であったロシアが大きな問題を抱えていたことは事実である。ニコライが皇帝になった時、ロシア人の80パーセントは読み書きができず、少なくとも半分の国民は貧困にあえいでいた。しかし、一部の勇敢な人々は改革に立ち上がり、地下革命党までつくった。ニコライは、自由主義を批判する人々に、議会政治への期待は「無意味な夢」に過ぎないと警告した。20世紀初頭、ストライキ、暴動、政治的暗殺、流血のポグロム(ユダヤ人大虐殺)が起こった。ニコライは無謀な使命感に駆られ、極東地域をロシアの勢力下に置こうとしたが、これが1904年の日本との戦争の引き金となり、ロシアの連戦連敗につながった。
1905年が転機となった。1月、戦争終結と労働条件の改善を求める平和的なデモが冬宮殿で行われ、軍隊がこれに発砲した。”血の日曜日”と呼ばれるこの事件は、皇帝の慈悲深い神話を崩壊させた。黒海艦隊の反乱、鉄道や工場労働者のストライキ、街頭でのデモなど、革命が国を覆い尽くした。皇帝は良心に反して行動せざるを得なくなった。10月宣言を発表し、臣民に市民的自由と議会(ドゥーマ)を認めたのである。独裁政治は終わったが、ニコライは自分が独裁者であることに変わりはないと主張した。彼は、第一次、第二次ドゥーマをあまりに急進的だとして却下した。政府は、より協力的な議員集団を確保するために選挙方式を変更したが、第三回ドゥーマはしばしば独立性を主張し、政府に対してかなり批判的であった。
ニコライ2世の波乱に満ちた人生と悲劇的な死を共にした女性が、ヘッセン王女アリックスである。彼女は1872年6月6日、ドイツの美しい町ダルムシュタットで生まれた。父ルイは大公、母アリスはヴィクトリア女王の9人の子供のうち3番目で、知的で内省的な女性であり、深い宗教心を持った人だった。アリックスが6歳の時に母が亡くなり、少女は憂鬱で、病的で、内気な性格になった。アリックスは、自分の感情を守り、他人から自分を隔離する反応をとった。祖母のヴィクトリア女王は、アリックスが十分な教育を受けた、礼儀正しい女性になるようにと配慮した。アリックスは、不器用で頑固、ルーテル派の信仰に深く傾倒していたが、絵も上手で、ピアノも得意だった。
ニコライがアリックスと出会ったのは、1884年、姉のエリザベスと叔父のセルゲイ・アレクサンドロヴィッチの結婚式のためにロシアに来たときだった。5年後の1889年、アリックスはエリザベスと一緒にサンクトペテルブルクで冬を過ごすことになった。ニコライは美しいドイツ人女性と恋に落ちたが、両親はアリックスを妻にしようとする息子の決意に納得がいかなかった。アリックスの冷たく飄々とした態度は、将来の皇后になるにはハンディキャップとなると考えたのだ。アリックスは、正教に改宗することにも難色を示した。しかし、ニコライは粘り強く説得し、1894年4月、二人は婚約をした。
1894年10月20日、アレクサンドル3世が死去した。翌日、アリックスはアレクサンドラ・フョードロヴナとして正教会に入信し、父の葬儀の一週間後にニコライと結婚した。もちろん、このタイミングは最悪だった。「彼女は棺桶の後ろに隠れて、私たちのところに来たのです」と、人々はささやいた。結婚生活は幸せで情熱的なものであったが、新皇后はその役割に不向きで、皇位に禍根を残すという初期の印象を拭い去ることはできなかった。
アレクサンドラのいとこであるルーマニアのマリー王妃は、アレクサンドラが「滅多に笑わないし、笑ってもわざとらしくで不機嫌だった」と回想している。アレクサンドラは美しく、魅力的であった。また、深い義務感を持っており、常に正しいことを行おうとした。しかしマリーは、彼女がどこか「『勝つ者』の仲間ではない」ことに気づいた。「あまりにも不信感が強く、守りに入りすぎている」のだ。アレクサンドラは、飄々とした態度でサンクトペテルブルクのエリートたちを遠ざけ、その快楽主義と呼ばれるものを否定した。ニコライ2世の母マリア・フフョードロヴナ(Maria Fedorovna)と比較されるほどだった。このような批判を受け、アレクサンドラは次第に私的な生活へと退いていった。
ニコライとアレクサンドラは、ツァールスコエ・セローのアレクサンドル宮殿に住んでいた。”ツァーリ村”は、サンクトペテルブルクから南へ15マイル離れた高級住宅地で、鉄柵に囲まれ、緋色のコサックたちが巡回していた。ニコライとアレクサンドラは、一緒に本を読み、公園を散歩し、心地よいお茶を楽しみ、互いの輝きに浸っていた。アリックスはニコライと出会ったとき、ロシア語は話せなかった。二人の共通語は英語で、その言語でコミュニケーションをとる習慣を身につけた。アレクサンドラはロシア語をマスターしたが、使いこなすまでには何年もかかった。1916年、彼女は夫にこう自慢げに書いた。「私はもう大臣たちを少しも恥ずかしがったり怖がったりせず、ロシアで滝のように話すことができます」。そして、”彼らは親切にも私の欠点を笑ったりはしない “と付け加えた。
アレクサンドラは1895年11月から1901年6月にかけて、4人の女の子を出産した。オルガ、タチアナ、マリア、そしてアナスタシアである。両親は美しく、魅力的で、才能に恵まれた娘たちを溺愛した。しかし、彼女たちには問題もあった。ニコライ2世は、王位を一族で維持するために息子を必要としていたのだ。皇帝パーヴェルは、母エカチェリーナ大帝をひどく嫌っていた。1796年にようやく即位した彼は、後継者法を改正し、女性が再びロシアを支配する可能性をほぼ排除してしまったのだ。アレクサンドラは、息子を産めないのは神の不興を買っているのだと考えた。正教会に改宗した皇后は、ほとんどのロシア人が不快に思うほどの熱心さで、新しい信仰に打ち込んだ。男児継承者という点では、奇跡を願っているようでもあった。ニコライは正教会で育ち、「神は万物を支配する」という教えを受動的に受け入れていた。ロシアでは、運命が宇宙を支配しているという古典的な考え方が主流である。すべては神の意志の産物であるから、出来事の意味を問うことに意味はないと考えていた。しかし、妻の見方は全く違っていた。
アレクサンドラは「運命」を信じていなかったようだ。少なくとも、祈りが未来を左右することは信じていたようだ。彼女はおそらく、怒った神が最初はソドムを滅ぼそうとしたが、アブラハムが思い切って交渉し、最後に「正しい人が10人いれば、この町は助かる」と約束したことを思い出したのだろう。神は考えを変えることができるのだ、という教訓である。アレクサンドラもまた、神は自分の重荷を背負ってくれる人を人生に置くことができると考えていた。神学院の指導者であり、彼らの告解者であったフェオファンは、この件に関して皇室夫妻に影響を与えた。フェオファンは、「神の手下はまだ地上にいる。聖なるロシアには、今日も聖人がたくさんいる。神は正しい人の姿を借りて、折に触れて民衆に慰めを送り、彼らは聖なるロシアの主役なのだ」と。この言葉に励まされたニコライとアレクサンドラは、農民やヒーラー、聖なる愚か者たちを次々とアレクサンドル宮殿に招き入れた。彼らは、これらの男女が、祈りによって、あるいは皇后の理解できない神秘的な力を引き出して、皇后を助けてくれることを期待したのである。しかし、ラスプーチンの前にいた一行の中で最も重要な人物は、実は外国人であった。ムッシュ・フィリップ。
1849年、サヴォワに生まれたフィリップ・ナジエ=ヴァショは、肉屋の職を捨て、霊的な力を身につけることにした。リヨンの医学部を退学になった後、彼は「オカルト医学」と呼ばれる、「心霊液とアストラルフォース」による治療を実践した。無免許医として逮捕されたこともあったが、多くの熱烈な信奉者がいた。ニコライとアレクサンドラは、1901年にフランスを訪れた皇帝がモンテネグロ人のアナスタシアとミリツァの姉妹を通してフィリップと知り合った。彼らは、ナジエ=ヴァショが、彼の言うところの「ヘルメス医学、天文学、精神医学の最も超越した実践」を通じて、胎児の性別を選択することができると主張していることに感銘を受けたのである。ニコライはこのフランス人をロシアに招いた。
フィリップ医師は、サンクトペテルブルクで3年間、多忙な日々を送った。患者は、背が低く陽気なこのフランス人を「我々の父」「主」と呼び、彼が手を置いて奇跡的な治癒を宣言すると、喜んでいた。ニコライ2世は彼に医者の免状を与え、一時期ナジエ=ヴァショはツァールスコエ・セローを訪れた。アレクサンドラは彼を “我らが友 “と呼んだ。ナジエ=ヴァショの「自分や仲間が見えなくなる魔法の帽子を持っている」という話を、多くのロシア人が真に受けていた。
ナジエ=ヴァショは、1902年の夏に皇后が男の子を妊娠したと宣言した。アレクサンドラは体重も増えたが、ヒステリックな妊娠であった。スキャンダルを防ぐため、宮殿からの速報でアレクサンドラは流産したと発表された。しかし、アレクサンドラを始めとする家族は唖然とし、怒りに震えた。
1903年末にアレクサンドラが妊娠しても、ナジエ・ヴァショを帰国させる圧力は続いた。ニコライはついに、批評家の言う通り、”我らが友 “と別れる時が来たと判断した。アレクサンドラも複雑な心境であったが、夫の決心が固まった時、夫に頭を下げたという事実は、この物語を進める上で心に留めておく必要がある。この別れは辛いものだったが、フランスの神秘主義者は、皇后に別れの贈り物をした。皇后はこの贈り物を大切にした。数年後、夫に宛てた手紙の中で、皇后は「この鐘のついた像は、正しくない者たちに警告を与え、彼らが近づかないようにするもので、私は(彼らの)悪を感じ、こうしてあなたを彼らから守るでしょう」と述べている。また、ナジエ・ヴァショは予言も残している。”いつの日か私のような友が現れ、神について語るだろう” ナジエ=ヴァショは1905年、フランスに帰国後すぐに亡くなった。
1904年7月30日、アレクサンドラはついに男の子を出産した。ニコライは日記に「私たちにとって忘れがたい、素晴らしい日だ」と記した。ニコライはその子を、ロマノフ家の二代目皇帝にちなんでアレクシスと名づけた。アレクシスは、有名な息子のピョートル大帝とは異なり、近代化や科学よりも宗教を重んじる伝統的な支配者だった。ニコライ2世は、独裁者が支配し、臣下が王位に揺るぎない忠誠心を示した、シンプルな過去に戻りたいという政治的な意思表示をしていたのである。
「アレクシスは家族の中心であり、すべての希望と愛情の的であった」と、ある皇室の家庭教師は書いている。彼は両親の誇りであり、喜びであった。しかし、喜びはすぐに絶望に変わった。アレクシスの誕生から6週間後、ニコライは「アリックスと私はとても心配している」と書いている。「今朝、小さなアレクシスのへそから何の原因もなく出血が始まった。夕方まで何度か止まりながら続いた」と。出血は3日目に止まりました。しかし、それからの数ヶ月、ツァレーヴィチはハイハイをしたり、転んだりしているうちに、手足に黒ずんだ醜いあざができるようになった。1歳の誕生日を前にして、ベビーカーから落ちた時の泣き声は、異常に耳障りだった。そして、診断が下された。アレクシスは血友病だったのだ。
「陛下、ツァレーヴィチの病気が完全に治癒することはないことをご理解ください」と、セルゲイ・フェドロフ医師は警告した。「血友病の発作は、ときどき再発するのです。転倒、切り傷、ひっかき傷から皇太子を守るため、厳しい保護措置が必要です。わずかな出血が命取りになるかもしれないのですから」。
血友病は遺伝性の疾患である。血友病の遺伝子を持つ母親は、統計上2人に1人の割合で息子に血友病を遺伝させる。この遺伝子の異常により、アレクシスの血液は正常な凝固に必要な凝固因子が欠乏しており、わずかな切り傷でも治るのに数時間から数日かかってしまう。しかし、最も危険なのは、ちょっとした衝撃で大量の内出血を起こすことである。もし、外科医がその損傷を修復するために手術をすれば、患者は出血多量で死んでしまうだろう。この時代には、モルヒネ、アヘン、コカインなどの鎮痛剤も出回っていた。ロマノフ家の人たちは、自分たちには使っていたようだが、なぜかアレクシスには使わなかったらしい。血友病の発作を放置したため、彼は想像を絶する苦痛を強いられた。
「この病気は我が家にはない」。1853年に生まれたばかりの息子レオポルドに血友病の恐ろしい症状が現れたとき、ヴィクトリア女王は困惑しながら抗議した。実際、ヨーロッパの王室に血友病を持ち込んだのは「おばあちゃん」だと非難されている。この病気は、彼女の遺伝子の自然変異か、父親から受け継いだX染色体の変異によるものであった。いずれにせよ、レオポルドはこの病気にかかり、妹のアリスとベアトリスは保因者であった。ベアトリスは、スペイン王室に血友病を持ち込んだ。アリスはもちろん、後にロシア皇后となるアレクサンドラの母である。アリスは息子のフリードリヒにも伝染し、彼は2歳の時に出血で死亡した。アリスの娘イレーネは、カイザー・ヴィルヘルム2世の弟ハインリヒと結婚し、その息子2人が血友病にかかった。一人目のヴィルヘルム王子は1889年に生まれ、1945年に亡くなるまで血友病の発作に悩まされた。二人目のハインリヒ皇太子は、1904年にアレクシスが生まれるわずか数日前、4歳で亡くなった。内出血が原因であった。
アレクサンドラは血友病についてある程度理解していたはずだ。この頃、血友病が話題になり始めていたのだから、彼女の家族もその危険性について多少なりとも知っていたはず。アレクサンドラの叔父、兄、そして2人の甥が血友病患者であった。自分が血友病をうつしたかもしれないと思ったのだろうか。ニコライやアレクサンドラがその可能性を考えた形跡はない。息子の病気の知らせはまったくの驚きであり、ショックだったようだ。ニコライは息子の病気を自分の人生と同じように受け止めたが、妻はこのような事態の意味を探った。そして、アレクシスの病気が自分のせいであることに気づいた。
「皇室のご両親は、生きる意味を失ってしまったんです」。ミハイロヴィチは、こう振り返った。「私も妻も、ご両親の前では笑うことができませんでした。宮中を訪れる時は、喪に服している時と同じように振る舞いました」。アレクサンドラは、「専門家の医学的見解」を最終的な結論として受け入れることを拒んだ。彼女は医師が無知であり、祈りが人生の問題への答えであると確信していた。しかし、祈るにはそれ相応の信仰が必要である。健康を守り、独裁政治と彼女の夫に反対する者たちを打ち負かすことのできる、彼女のとりなし手となる男か女が必要だったのだろう。
そして、この少年の不幸が、奇跡を起こす人の舞台となっていった。
つづきを読む ラスプーチンとはどんな人?『ラスプーチン知られざる物語』4
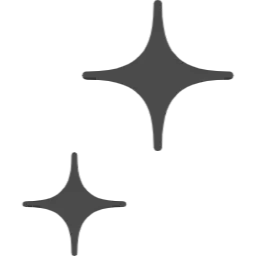
アクセス・バーズはどこから来ているのか?アクセス・コンシャスネスの教えはいったいどこから?
そういった疑問には、やはりこの人【ラスプーチン】を知らなくては始まりません。
ということで、Rasputin Untold Story by Joseph T. Fuhrmann ジョセフ・T・フールマン『ラスプーチン知られざる物語』を読みこもうという試みです。

